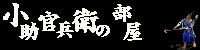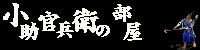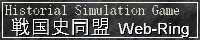| 【備中国】 |
| 横手山城 | 〒715-0019 岡山県井原市井原町 |  | |
| 工ヶ城 | 〒715-0017 岡山県井原市下稲木町 |  | |
| 戸木荒神山城 | 〒715-0022 岡山県井原市下出部町 |  | |
| 落石城 | 〒715-0024 岡山県井原市高屋町 |  | |
| 高屋城 | 〒715-0024 岡山県井原市高屋町 |  | |
| 山手城 | 〒715-0024 岡山県井原市高屋町 |  | |
| 小見山城 | 〒715-0024 岡山県井原市高屋町 |  | |
| 鎌田城 | 〒715-0021 岡山県井原市上出部町 |  | |
| 青蔭城 | 〒715-0006 岡山県井原市西江原町 |  | 那須氏一族の大山氏の城。 |
| 中堀城 | 〒715-0006 岡山県井原市西江原町 |  | 那須頼隆の次男那須光隆が築城。那須政隆の代で足利尊氏に下野国中新郷を賜わった。 |
| 亀迫城 | 〒715-0003 岡山県井原市東江原町 |  | 備中侵攻のため毛利元清が築城。宍戸隆家(宍戸安芸守)を城主として配置。 |
| 小菅城 | 〒715-0003 岡山県井原市東江原町 |  | 小菅山城ともいう。鎌倉初期(1192〜1241年)に那須宗晴が築城。那須宗隆(那須与一)は丹後国五賀荘、信濃角豆荘、若狭国東宮川荘、武蔵国太田荘などとともに備中国荏原荘の地頭職を得て、那須宗晴が下向し小菅城を築城。 |
| 白実城 | 〒715-0003 岡山県井原市東江原町 |  | 天正年間(1573〜1593年)に毛利家臣木村平内、神田六郎兵衛らが居城とした。 |
| 高越山城 | 〒715-0003 岡山県井原市東江原町 |  | 高越城ともいう。弘安4年(1281年)に宇都宮貞綱が築城。享徳2年(1453年)に伊勢長行(伊勢新左衛門)が六庄三百貫の知行を得て伊勢より移住。伊勢盛時(伊勢宗瑞、北條早雲、伊勢新九郎)は、伊勢盛定の子として生まれ、妹の嫁ぎ先である駿河国今川氏に身を寄せた。 |
| 米持城 | 〒715-0003 岡山県井原市東江原町 |  | |
| 宇戸谷茶臼山城 | 〒714-1402 岡山県井原市美星町宇戸谷 |  | |
| 土居山城 | 〒714-1404 岡山県井原市美星町烏頭 |  | |
| 小笹丸城 | 〒714-1407 岡山県井原市美星町黒忠 |  | 竹野井氏の居城。永正年間(1504〜1520年)には竹野井市朗衛門尉が居城。天正3年(1575)には竹野井氏高、竹野井春高が城主。 |
| 金黒山城 | 〒714-1415 岡山県井原市美星町星田 |  | 三村氏の本拠地。三村家親のときに星田から成羽へ移住。その後三村家親の叔父三村為親が在城した。 |
| 法雲山城 | 〒714-1415 岡山県井原市美星町星田 |  | |
| 岩崎城 | 〒714-1415 岡山県井原市美星町星田 |  | |
| 尼子城 | 〒714-1415 岡山県井原市美星町星田 |  | 出雲の尼子家久が在城した。 |
| 星田茶臼山城 | 〒714-1415 岡山県井原市美星町星田 |  | 茶臼城ともいう。 |
| 木之山城 | 〒714-2103 岡山県井原市芳井町宇戸川 |  | |
| 井戸橋城 | 〒714-2231 岡山県井原市芳井町下鴫 |  | 下鴫城、足利城ともいう。治承年間(1177〜1180年)に足利忠綱が築城。 |
| 雄瀬山城 | 〒714-2101 岡山県井原市芳井町梶江 |  | |
| 正霊山城 | 〒714-2111 岡山県井原市芳井町吉井 |  | 正雪山城ともいう。下野国小山氏の支族小山政秀が下野国那賀郡藤井郷を領し藤井氏を称したことにはじまる藤井好重によって築かれた。 |
| 小屋ノ山城 | 〒714-2122 岡山県井原市芳井町種 |  | 建武2年(1336年)に刈谷佐衛門(刈谷左衛門)が築城。 |
| 高原城 | 〒714-2232 岡山県井原市芳井町上鴫 |  | 城山城ともいう。関東管領上杉顕定の次男小鼻直顕が伊勢盛時に追われて越後に逃れたのち、大内氏の援助で2800貫の所領を得て高原城を築城。小畠氏を称した。天文19年(1550年)に落城。 |
| 中山城 | 〒714-2114 岡山県井原市芳井町川相 |  | 河合城、川相城ともいう。文明2年(1470年)に河合行重(河合豊前守)が築城。藤井氏との婚姻関係により勢力を拡大したが毛利氏の台頭により衰退し毛利氏に従った。 |
| 天神山古城 | 〒714-2113 岡山県井原市芳井町天神山 |  | 河合行重(河合豊前守)が築城。 |
| 能多ヶ丸城 | 〒714-2102 岡山県井原市芳井町与井 |  | |
| 才崎城 | 〒715-0004 岡山県井原市木之子町 |  | 正中年間(1324〜1325年)に渡辺大隅守が築城。 |
| 冠山城 | 〒701-1464 岡山県岡山市北区下足守 |  | 河津氏明(河津左衛門尉)が築城。林重真や守福寺氏が守ったともされる。 |
| 加茂城 | 〒701-1342 岡山県岡山市北区加茂 |  | 鴨城、鴨庄城、岡崎城ともいう。岡本隼人が城主。桂廣重、上山元忠、生石中務少輔が築城。 |
| 高松城 | 〒701-1335 岡山県岡山市北区高松 |  | 石川氏が築城。 |
| 小山城 | 〒701-1352 岡山県岡山市北区小山 |  | |
| 忍山城 | 〒701-1525 岡山県岡山市北区上高田 |  | |
| 庭瀬城 | 〒701-0153 岡山県岡山市北区庭瀬 |  | |
| 撫川城 | 〒701-0164 岡山県岡山市北区撫川 |  | 高下ノ城、芝揚城、泥城、小倉城ともいう。寛治年間(1087〜1094年)に藤井久任が築城。 |
| 生石城 | 〒701-1351 岡山県岡山市北区門前 |  | 報恩寺山陣場ともいう。 |
| 菅野城 | 〒716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川 |  | |
| 丸山城 | 〒716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川 |  | |
| 離小屋城 | 〒716-1131 岡山県加賀郡吉備中央町上竹 |  | |
| 野路山城 | 〒716-1131 岡山県加賀郡吉備中央町上竹 |  | |
| 佐与谷城 | 〒716-1554 岡山県加賀郡吉備中央町西 |  | |
| 馬越城 | 〒716-1552 岡山県加賀郡吉備中央町岨谷 |  | |
| 上ヶ城 | 〒716-1122 岡山県加賀郡吉備中央町竹荘 |  | |
| 坂元城 | 〒709-2343 岡山県加賀郡吉備中央町竹部 |  | |
| 山崎城 | 〒709-2343 岡山県加賀郡吉備中央町竹部 |  | |
| 大原城 | 〒716-1111 岡山県加賀郡吉備中央町田土 |  | |
| 櫻坂城 | 〒716-1111 岡山県加賀郡吉備中央町田土 |  | |
| 川西城 | 〒716-1111 岡山県加賀郡吉備中央町田土 |  | |
| 小谷城 | 〒716-1112 岡山県加賀郡吉備中央町湯山 |  | |
| 大畑城 | 〒716-1112 岡山県加賀郡吉備中央町湯山 |  | |
| 矢倉城 | 〒716-1121 岡山県加賀郡吉備中央町納地 |  | 矢倉山城ともいう。鎌倉時代後期に田中盛兼が築城。天正年間(1573〜1593年)には田中直重が三村氏に従っていたが、毛利氏の侵攻により追われた。 |
| 羽子田城 | 〒716-1101 岡山県加賀郡吉備中央町豊野 |  | |
| 古和田城 | 〒716-1551 岡山県加賀郡吉備中央町北 |  | 野山城ともいう。文明15年(1483年)に野山庄勝が築城。伊達朝義(伊達弾正)が備中国野山荘の地頭として入部したことにはじまる。 |
| 大和佐山城 | 〒716-1551 岡山県加賀郡吉備中央町北 |  | |
| 園井城 | 〒714-0021 岡山県笠岡市園井 |  | |
| 笠岡山城 | 〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡 |  | 笠岡古城、笠岡西浜の城、笠岡城ともいう。元徳3年・元弘元年(1331年)に陶山義高(陶山藤三郎)が築城。永正年間(1504〜1520年)に大内氏の勢力がおよぶと陶山氏にかわり井上春忠が居城とした。 |
| 鳶ノ子城 | 〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡 |  | |
| 西浜城 | 〒714-0057 岡山県笠岡市金浦 |  | |
| 広浜城 | 〒714-0023 岡山県笠岡市広浜 |  | |
| 馬鞍山城 | 〒714-0007 岡山県笠岡市山口 |  | |
| 仮名沢城 | 〒714-0077 岡山県笠岡市篠坂 |  | |
| 篠坂城 | 〒714-0077 岡山県笠岡市篠坂 |  | |
| 小平井城 | 〒714-0012 岡山県笠岡市小平井 |  | |
| 政所山城 | 〒714-0005 岡山県笠岡市新賀 |  | |
| 諏訪山城 | 〒714-0005 岡山県笠岡市新賀 |  | |
| 城山城 | 〒714-0037 岡山県笠岡市真鍋島 |  | |
| 沢津城 | 〒714-0037 岡山県笠岡市真鍋島 |  | |
| 真鍋城 | 〒714-0037 岡山県笠岡市真鍋島 |  | |
| 小見山城 | 〒714-0044 岡山県笠岡市神島 |  | |
| 大道城 | 〒714-0044 岡山県笠岡市神島 |  | |
| 鳥越城 | 〒714-0044 岡山県笠岡市神島 |  | |
| 福浦城 | 〒714-0044 岡山県笠岡市神島 |  | |
| 竜王山城 | 〒714-0014 岡山県笠岡市相生 |  | |
| 楢村城 | 〒714-0001 岡山県笠岡市走出 |  | |
| 折敷山城 | 〒714-0001 岡山県笠岡市走出 |  | 尾敷山城、尾鋪山城ともいう。天文年間(1532〜1555年)に有岡氏の居城。 |
| 大橋山城 | 〒714-0061 岡山県笠岡市大宜 |  | |
| 小丸山城 | 〒714-0003 岡山県笠岡市尾坂 |  | |
| 高丸城 | 〒714-0062 岡山県笠岡市茂平 |  | |
| 前影山城 | 〒714-0062 岡山県笠岡市茂平 |  | |
| 入田城 | 〒714-0075 岡山県笠岡市有田 |  | |
| 有田城 | 〒714-0075 岡山県笠岡市有田 |  | |
| 森山城 | 〒714-0066 岡山県笠岡市用之江 |  | |
| 明知城 | 〒714-0066 岡山県笠岡市用之江 |  | |
| 笹尾城 | 〒719-2232 岡山県高梁市宇治町宇治 |  | |
| 白毛ヶ城 | 〒719-2232 岡山県高梁市宇治町宇治 |  | |
| 丸山城 | 〒719-2233 岡山県高梁市宇治町穴田 |  | |
| 滝谷城 | 〒719-2234 岡山県高梁市宇治町本郷 |  | |
| 粧田山城 | 〒716-1311 岡山県高梁市巨瀬町 |  | |
| 下切城 | 〒716-0053 岡山県高梁市玉川町下切 |  | ツガン丸城ともいう。 |
| 玉ノ城山城 | 〒716-0052 岡山県高梁市玉川町玉 |  | |
| 秋町城 | 〒719-2122 岡山県高梁市高倉町田井 |  | |
| 陣山城 | 〒716-0066 岡山県高梁市松原町松岡 |  | |
| 馬之城 | 〒716-0066 岡山県高梁市松原町松岡 |  | |
| 広瀬固屋城 | 〒716-0051 岡山県高梁市松山 |  | |
| 成羽城 | 〒716-0111 岡山県高梁市成羽町下原 |  | |
| 鶴首城 | 〒716-0111 岡山県高梁市成羽町下原 |  | 文治5年(1189年)に河村秀清が築城。天文2年(1533年)に本格的に三村家親が築城した。 |
| 高ノ盛城 | 〒716-0113 岡山県高梁市成羽町佐々木 |  | 鵠ノ森山城ともいう。 |
| 小金山城 | 〒719-2341 岡山県高梁市成羽町吹屋 |  | |
| 三村城 | 〒716-0121 岡山県高梁市成羽町成羽 |  | 成羽城ともいう。天文2年(1533年)に三村家親が築城。 |
| 長地城 | 〒716-0334 岡山県高梁市成羽町長地 |  | |
| 中村城 | 〒716-0335 岡山県高梁市成羽町布寄 |  | |
| 折居城 | 〒716-0223 岡山県高梁市川上町高山 |  | |
| 中山城 | 〒716-0223 岡山県高梁市川上町高山 |  | |
| 野田城 | 〒716-0203 岡山県高梁市川上町三沢 |  | |
| 国吉城 | 〒716-0202 岡山県高梁市川上町七地 |  | 手ノ庄城ともいう。元弘年間(1331〜1334年)に安藤元理が築城。 |
| 小社森城 | 〒716-0201 岡山県高梁市川上町地頭 |  | |
| 寺山城 | 〒719-2121 岡山県高梁市川面町 |  | |
| 城平城 | 〒719-2121 岡山県高梁市川面町 |  | |
| 城山城 | 〒719-2402 岡山県高梁市中井町西方 |  | |
| 加葉山城 | 〒719-2401 岡山県高梁市中井町津々 |  | |
| 津々城 | 〒719-2401 岡山県高梁市中井町津々 |  | |
| 松山城 | 〒716-0004 岡山県高梁市内山下 |  | 高梁城ともいう。仁治元年(1240年)に秋庭重信が臥牛山の大松山に築城。 |
| 戸構城 | 〒716-0323 岡山県高梁市備中町西山 |  | |
| 軽尾城 | 〒716-0322 岡山県高梁市備中町西油野 |  | |
| 袈裟尾城 | 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野 |  | |
| 勝負城 | 〒716-0304 岡山県高梁市備中町布賀 |  | |
| 紫城 | 〒716-0311 岡山県高梁市備中町平川 |  | |
| 平川城 | 〒716-0311 岡山県高梁市備中町平川 |  | |
| 金子山城 | 〒716-0311 岡山県高梁市備中町平川 |  | |
| 大原田城 | 〒716-0311 岡山県高梁市備中町平川 |  | |
| 有漢常山城 | 〒716-1321 岡山県高梁市有漢町有漢 |  | 鎌倉時代に秋庭重信が築城。 |
| 有漢飯ノ山城 | 〒716-1321 岡山県高梁市有漢町有漢 |  | 伊山国重の城。後に毛利氏に属した山縣国吉が守った。天正8年(1580年)4月に毛利輝元が備前虎倉城を攻めた軍に従軍した山縣国吉は上加茂で宇喜多勢の伏兵にあい討死。毛利軍は敗走した。 |
| 台ヶ鼻城 | 〒716-1321 岡山県高梁市有漢町有漢 |  | 承久3年(1221年)に秋庭重信が築城。 |
| 秋庭城 | 〒716-1321 岡山県高梁市有漢町有漢 |  | 鎌倉時代に秋庭重信が築城。 |
| 阿部深山城 | 〒716-0063 岡山県高梁市落合町原田 |  | |
| 庄城 | 〒714-1212 岡山県小田郡矢掛町横谷 |  | |
| 花房城 | 〒714-1212 岡山県小田郡矢掛町横谷 |  | |
| 原城 | 〒714-1212 岡山県小田郡矢掛町横谷 |  | |
| 猿掛城 | 〒714-1212 岡山県小田郡矢掛町横谷 |  | 南北朝初期に庄資政が築城。庄氏は武蔵国児玉党の出自。源平合戦の功により地頭職を得て下向し、幸山城を拠点とした。庄資政のときに猿掛城を築き拠点を移した。室町時代には守護代となり、天文2年(1533年)に庄為資は上野伊豆守を攻め滅ぼし松山城主となり、猿掛城には一族の庄実近を配置。天文22年(1553年)に鶴首城主三村家親は毛利氏の支援を受け猿掛城に攻め寄せるが勝敗はつかず、三村家親の子三村元祐を庄為資の養子とすることで和議が整い、三村元祐が城主となった。 |
| 下高末城 | 〒714-1204 岡山県小田郡矢掛町下高末 |  | |
| 伽藍山城 | 〒714-1226 岡山県小田郡矢掛町江良 |  | |
| 神戸山城 | 〒714-1227 岡山県小田郡矢掛町小田 |  | |
| 岩屋山城 | 〒714-1227 岡山県小田郡矢掛町小田 |  | |
| 神子山城 | 〒714-1202 岡山県小田郡矢掛町小林 |  | |
| 小林城 | 〒714-1202 岡山県小田郡矢掛町小林 |  | |
| 龍山城 | 〒714-1225 岡山県小田郡矢掛町浅海 |  | |
| 太郎丸城 | 〒714-1225 岡山県小田郡矢掛町浅海 |  | |
| 中山城 | 〒714-1215 岡山県小田郡矢掛町中 |  | |
| 山本城 | 〒714-1211 岡山県小田郡矢掛町東三成 |  | |
| 要害山城 | 〒714-1211 岡山県小田郡矢掛町東三成 |  | |
| 山田古城 | 〒714-1214 岡山県小田郡矢掛町南山田 |  | |
| 船ヶ迫山城 | 〒714-1214 岡山県小田郡矢掛町南山田 |  | |
| 矢掛茶臼山城 | 〒714-1201 岡山県小田郡矢掛町矢掛 |  | 天正年間(1573〜1593年)に毛利元清が築城。 |
| 塩城山城 | 〒718-0001 岡山県新見市上熊谷 |  | 多治備中守の城。天正3年(1575年)の備中兵乱のときに毛利方に与した多治部景治(多治部雅楽頭)は楪城を攻略。 |
| 楪城 | 〒718-0005 岡山県新見市上市 |  | 紅城、弓絵葉城ともいう。治承4年(1180年)に新見祐信(新見四郎兵衛尉)が築城。文明4年(1472年)に楪惟久が城主のときに、備中松山城城主上野広長に攻められ落城。上野広長は三男上野維行(上野内藤)を城番とした。文亀元年(1501年)に上野維行のとき、新見国経(新見蔵人)が楪城を攻め、上野維行を備中松山へ退去させる。永正8年(1511年)に秋庭利元(秋庭備中守)が楪城を攻略するも、永正15年(1518年)に新見国経が秋庭氏を攻略。天文2年(1533年)に猿掛城城主庄為資が備中松山城を攻略するときに楪城城主上野行経(上野左京亮)も討死し、上野氏は滅亡。
庄為資は楢崎時信(楢崎久之丞)を城番とした。永禄9年(1566年)に新見貞経が城主のとき、毛利方の三村家親に攻められ落城。元亀2年(1571年)に毛利軍は城主楢崎時忠(楢崎助四郎)を攻略し、三村元範(三村宮内少輔)を城主とした。のちに毛利家臣今田経高(今田上野介)、天野勝元らが城主をつとめた。 |
| 朝倉城 | 〒718-0005 岡山県新見市上市 |  | |
| 粒根城 | 〒718-0005 岡山県新見市上市 |  | 天正3年(1575年)に楪城を追われた三村元範が助けを求め、粒根城主伊勢国寛(伊勢掃部入道)と竹野城主三村元威(三村左介)は三村元範に与して多治部景治に対抗するが、三村元範は討死。 |
| 鳶ヶ巣城 | 〒718-0011 岡山県新見市新見 |  | 南北朝時代初期に楢崎利景が築城。山名氏、尼子氏に仕えた。戦国時代には楢崎豊景(楢崎春景)が居城とした。毛利氏に属して永禄4年(1561年)に備後国芦田郡久佐に領地替えとなった。その後尼子家臣徳光兵庫守が在城。 |
| 新見城 | 〒718-0011 岡山県新見市新見 |  | |
| 角尾城 | 〒718-0011 岡山県新見市新見 |  | 三村家親の子三村元高が築城。 |
| 小谷山城 | 〒718-0011 岡山県新見市新見 |  | |
| 見坂山城 | 〒719-3611 岡山県新見市神郷下神代 |  | 武坂城ともいう。応永年間(1394〜1428年)に細川一族の羽場頼房が築城。 |
| 勝ヶ城 | 〒719-2802 岡山県新見市神郷高瀬 |  | |
| 小郷寺城 | 〒719-2802 岡山県新見市神郷高瀬 |  | |
| 重藤城 | 〒719-3612 岡山県新見市神郷油野 |  | |
| 竹野城 | 〒718-0017 岡山県新見市西方 |  | |
| 石蟹山城 | 〒718-0015 岡山県新見市石蟹 |  | 三村一族の石蟹守元(石蟹元宣、石蟹与兵衛)が城主。天文年間(1532〜1555年)に石蟹守元は尼子氏に捕らわれ出雲国富田城に13年ほど蟄居させられた。石蟹守元の妻は庄氏敬の娘。天文22年(1553年)に毛利氏と三村氏の連合軍が庄氏の猿掛城を攻めたおりには、一族の三村氏ではなく庄氏に与した。 |
| 赤坂城 | 〒718-0104 岡山県新見市千屋花見 |  | |
| 実山城 | 〒718-0102 岡山県新見市千屋実 |  | |
| 土井城 | 〒718-0102 岡山県新見市千屋実 |  | |
| 川崎城 | 〒719-2641 岡山県新見市草間 |  | |
| 城山城 | 〒719-2642 岡山県新見市足見 |  | |
| 円通山城 | 〒719-3504 岡山県新見市大佐永富 |  | |
| 割亀山城 | 〒719-3503 岡山県新見市大佐小阪部 |  | |
| 周防城 | 〒719-3507 岡山県新見市大佐小南 |  | |
| 葛籠畑山城 | 〒719-3502 岡山県新見市大佐上刑部 |  | |
| 安本城 | 〒719-3506 岡山県新見市大佐田治部光吉 |  | |
| 大山城 | 〒719-3505 岡山県新見市大佐布瀬 |  | |
| 鯉滝城 | 〒718-0014 岡山県新見市長屋 |  | |
| 岩高城 | 〒719-3702 岡山県新見市哲西町上神代 |  | |
| 岸本城 | 〒719-3811 岡山県新見市哲西町大竹 |  | 吉岡質休、吉岡通秀(吉岡右京)らの名が城主として残る。 |
| 育野城 | 〒719-3814 岡山県新見市哲西町大野部 |  | |
| 藤木城 | 〒719-3812 岡山県新見市哲西町畑木 |  | 茶臼山城ともいう。三村家臣吉良常陸守、吉良七郎左衛門尉らが城主。 |
| 西山城 | 〒719-3813 岡山県新見市哲西町八鳥 |  | 八鳥要害山城ともいう。文治元年(1185年)に市川行房が築城。市川氏は甲斐国八代郡市川の発祥。天文2年(1533年)に備後国五品嶽城主宮高盛が改修した。 |
| 豆木城 | 〒719-3701 岡山県新見市哲西町矢田 |  | 天文年間(1532〜1555年)に三村家臣吉良丹後守が築城。 |
| 土井城 | 〒719-3701 岡山県新見市哲西町矢田 |  | |
| 万石城 | 〒719-3701 岡山県新見市哲西町矢田 |  | 仁治年間(1240〜1243年)に備中国松山城主秋庭重信の弟秋庭重光が築城。 |
| 旗山城 | 〒718-0305 岡山県新見市哲多町荻尾 |  | |
| 助正城 | 〒718-0302 岡山県新見市哲多町花木 |  | |
| 鎌ヶ畝城 | 〒718-0311 岡山県新見市哲多町蚊家 |  | |
| 滝丸城 | 〒718-0301 岡山県新見市哲多町宮河内 |  | |
| 諏訪山城 | 〒718-0304 岡山県新見市哲多町成松 |  | |
| 成松山城 | 〒718-0304 岡山県新見市哲多町成松 |  | |
| 馬醉木城 | 〒718-0312 岡山県新見市哲多町田淵 |  | |
| 荒戸山城 | 〒718-0312 岡山県新見市哲多町田淵 |  | |
| 猿滝城 | 〒718-0303 岡山県新見市哲多町本郷 |  | |
| 越山城 | 〒718-0306 岡山県新見市哲多町矢戸 |  | |
| 井ノ畝城 | 〒718-0307 岡山県新見市哲多町老栄 |  | |
| 鬼山城 | 〒718-0012 岡山県新見市唐松 |  | |
| 甲籠城 | 〒718-0012 岡山県新見市唐松 |  | |
| 柏山城 | 〒719-2552 岡山県新見市法曽 |  | |
| 鳶ヶ城 | 〒719-2721 岡山県新見市豊永赤馬 |  | |
| 佐井田城 | 〒716-1421 岡山県真庭市下中津井 |  | 才田城、斎田城ともいう。永正14年(1517年)に植木秀長が築城。 |
| 丸山城 | 〒716-1433 岡山県真庭市下呰部 |  | |
| 鳶尾城 | 〒719-0301 岡山県浅口郡里庄町里見 |  | |
| 鴨山城 | 〒719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方 |  | 鴨方城、加茂山城、石井山城、清滝山城ともいう。鴨方細川氏の城。応永14年(1407年)に細川満国が築城。 |
| 安芸守山城 | 〒719-0234 岡山県浅口市鴨方町益坂 |  | |
| 杉山城 | 〒719-0241 岡山県浅口市鴨方町小坂東 |  | |
| 西知山城 | 〒719-0233 岡山県浅口市鴨方町地頭上 |  | |
| 龍王山城 | 〒719-0251 岡山県浅口市鴨方町六条院西 |  | |
| 泉山城 | 〒719-0252 岡山県浅口市鴨方町六条院中 |  | |
| 茶臼山城 | 〒714-0101 岡山県浅口市寄島町 |  | |
| 青佐山城 | 〒714-0101 岡山県浅口市寄島町 |  | |
| 龍王山城 | 〒719-0113 岡山県浅口市金光町佐方 |  | |
| 佐方城 | 〒719-0113 岡山県浅口市金光町佐方 |  | |
| 加賀山城 | 〒719-0104 岡山県浅口市金光町占見新田 |  | |
| 松島城 | 〒701-0114 岡山県倉敷市松島 |  | 梨羽高秋の城。 |
| 日幡城 | 〒701-0101 岡山県倉敷市日畑 |  | 日幡氏の城。毛利氏と羽柴氏が対峙した高松合戦では、毛利元就の娘婿である上原元祐が羽柴方に寝返り、城主日幡六郎兵衛にも寝返りを勧めた。日幡六郎兵衛はそれを断り上原元祐を討つべく本丸に帰ったところを、すでに上原元祐に内通していた弟と上原元祐の兵に槍で突かれて絶命した。 |
| 鬼ノ城 | 〒719-1101 岡山県総社市奥坂 |  | |
| 夕部山城 | 〒719-1145 岡山県総社市下原 |  | 伊与部山城、勝山城ともいう。天正3年(1575年)に明石兵部少輔が築城。 |
| 真壁城 | 〒719-1135 岡山県総社市溝口 |  | |
| 経山城 | 〒719-1105 岡山県総社市黒尾 |  | |
| 鬼身城 | 〒710-1202 岡山県総社市山田 |  | 文亀元年(1501年)から上田氏が代々在城。 |
| 亀山城 | 〒719-1123 岡山県総社市上林 |  | 天文年間(1532〜1555年)に佐野忠綱が築城。天正年間(1573〜1593年)には佐野忠職が城主をつとめた。 |
| 市場古城 | 〒710-1203 岡山県総社市新本 |  | 天正年間(1573〜1593年)に永井一虎が城主。永井重虎は関ヶ原合戦で行方が分からなくなった。 |
| 荒平山城 | 〒719-1142 岡山県総社市秦 |  | |
| 福山城 | 〒719-1171 岡山県総社市清音三因 |  | 鎌倉時代に真壁是久(真壁小六郎)が築城。 |
| 幸山城 | 〒719-1171 岡山県総社市清音三因 |  | 高山城、甲山城ともいう。延慶年間(1308〜1311年)に庄資房が築城。 |
| 長良山城 | 〒719-1111 岡山県総社市長良 |  | 八幡山古城ともいう。建武年間(1334〜1338年)に世野川道祐(世野左衛門入道)が築城。世野氏はのちに禰屋氏と改姓した。 |
| 鳥越山城 | 〒719-1102 岡山県総社市東阿曽 |  | 東阿曽城山、城山城ともいう。鳥越若狭守の居城。 |
| 木村山城 | 〒719-1146 岡山県総社市八代 |  | 元暦年間(1184〜1185年)に土肥実平が築城。 |
| 早島城 | 〒701-0304 岡山県都窪郡早島町早島 |  | 竹井将監の城。 |