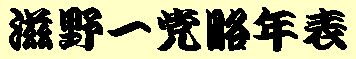
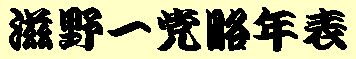
天平勝宝元年 |
楢原造東人(滋野東人)の名が見える。 楢原東人(滋野東人)は駿河守となり、駿河在任中、蒲原付近で金を採取して朝廷に献上している。 楢原東人(滋野東人)は大和国楢原(奈良県御所市)の地の豪族であり、 大和国六党の一党に数えられ、南党として知られる楢原氏は、大和国葛上郡楢原(奈良県御所市楢原)に住したことにはじまるという。 さらにその子孫は紀伊国(和歌山県)の紀伊国造である古代の名族紀氏にまでさかのぼることができる。 朝廷の覚えもめでたく、勤臣の姓を賜り住まいする地名を取って楢原造とも称した。 滋野氏のルーツは清和天皇ではなく、孝謙天皇時代に活躍し、 実在が実証できる楢原国造の楢原東人(滋野東人)を遠祖とした氏族である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天平勝宝2年 |
楢原造東人(滋野東人)の名が見える。 楢原造東人(滋野東人)が朝臣を賜る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神護景雲元年 | 楢原造東人(滋野東人)の長男滋野家譯(滋野尾張守家訳)が生まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安時代 |
滋野家譯(滋野尾張守家訳)の名が見える。 滋野家譯(滋野尾張守家訳)は宿祢の姓を賜る栄誉を受ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘仁元年 |
滋野家譯(滋野尾張守家訳)の長男滋野貞主の名が見える。 滋野貞主は朝臣の姓を賜る栄誉を受ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘仁14年 |
滋野家譯(滋野尾張守家訳)の名が見える。 滋野家譯(滋野尾張守家訳)は朝臣を賜る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天長8年 |
滋野貞主は当代一の学者で文章が巧みなことから、勅(天皇の命)によって多くの進歩的儒教者とともに秘府の図書を基にして、
類別を編纂した1000巻に及ぶ百科辞書『秘府略』や『経国集』20巻を著す。 滋野貞主は朝廷との結びつきが強く、娘二人を宮中に入れ、1人は仁明天皇の妃として本康親王を産み、 1人は文徳天皇の皇后として惟彦親王を産む。 滋野氏は朝廷と密接な関係になったこともあり、大いに繁栄し権勢を誇る。 滋野貞主の推薦で一族の者(滋野貞主の嫡男滋野善蔭ともされている)が信濃の国司に任ぜられ、信濃に下向したという。 そして信濃の豪族の娘との間に子どもをもうけ、その子に滋野姓を名乗らせた。これが信濃滋野氏の祖となったわけだが、 その子孫が数代続く間に、あいまいな歴史の中で滋野貞主と朝廷との密接な関係を、 朝廷の直属の親王と思いこみ、しかも惟彦親王が清和天皇の腹違いの兄であることから 清和天皇を祖先と思いこみ、清和源氏を名乗ったのではないかといわれている。 いずれにしても、平安時代末期には東信濃には、土着した国司の子孫と思われる滋野氏が根を張っていく。 「滋野三家」と称される海野氏・祢津氏・望月氏の三家は更に多くの支流を分布し、中信濃、西上野などに広まっていく。 海野氏ほか望月氏・祢津氏の二氏も、『保元物語』『平家物語』『吾妻鏡』などの諸史書にしばしば見える。 いわば信濃の名族にまでなっていた。 この滋野一族は、中信濃の筑摩・安曇の両郡、さらには上州吾妻郡にまで広がってもいく。 信濃と上野との境に連なる四阿山・浅間山・白根山の山麓一帯には、これらの山を崇拝する修験が発達した。 浅間系三山ともいうべきこれらの山山は、1つのまとまった地域で、この山麓一帯を根拠地とする武士の大部分は滋野一党である。 その多くは修験と関係を持つようになった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁寿2年 |
滋野貞主の名が見える。 滋野貞主は朝臣を賜る。 2月、滋野貞主が没す。享年は68歳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貞観10年 |
滋野恒蔭の名が『日本後記』『日本三大実録』などの諸史に見える。 滋野恒蔭は信濃の介に任ぜられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貞観12年 |
滋野善根の名が『日本後記』などの諸史に見える。 滋野善根は信濃守に任ぜられる。 滋野善言は信濃からの貢馬の駒牽きのことを司る役人として名を残しており、 滋野氏は信濃の守や介をつとめる理由もあって、代代『馬寮』と深い関係を持つ役職をつとめるようになっていったと思われる。 このことは必然的に信濃の諸牧とも強い絆で結ばれることとなり、 諸牧の代表的な望月牧や新張牧などの管理者であった望月氏や祢津氏および その中間にあたる海野の豪族と血縁関係までもつようになったともいわれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天慶元年 |
平将門に圧迫された平良兼の子平貞盛は、
この事情を京の朝廷に訴えようと東山道より京に向かう。
それを知った平将門は1000余の兵を率いて直ちに追撃に向かった。 平貞盛は危険を察して海野城(海野古城)へ逃げ込み、 旧知の滋野恒成(滋野善淵)に助けを求めた。 平将門は、平貞盛が海野城に隠れているのを知り、先回りして国分寺付近に陣を取り、 神川を挟んで衝突する。いわゆる千曲川合戦である。 小県郡の滋野一族は平貞盛に加勢して、平将門と千曲川にて合戦した。 滋野一族は奮戦したが、戦は平将門側が勝利を収め、平貞盛は付近の山中に逃れ危機を脱したといわれる。 なお、この戦いで、信濃国分寺が焼失したという。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天慶2年 | 桓武平氏の分流として関東に土着していた私営田領主の平氏一族の平将門と、 伯父平国香や叔父平良兼などを加えた一族の内輪同士の私闘は、種種の行き違いから乱は大きくなり、 紆余曲折の後に、平将門側の勝利に終わっている。勢いにのった平将門は新皇と称して、 関東の独立をはかったものの、まもなくこの反乱も鎮圧される。この事件は天慶の乱といわれている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天慶4年 | 滋野恒成(滋野善淵)は海善寺の開基となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天暦4年 |
滋野恒信(海野左馬権介幸俊)は望月牧監となり、信州小県郡海野に下向し、
海野幸俊に改名(海野氏を家名と)し、
滋野恒信(海野幸俊)は海野氏初代当主となる。海野氏(海野滋野氏)のはじまりである。
海野幸俊には弟依田敦重がおり、依田滋野氏の祖とされる。 ここに海野氏と依田氏がはじまる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天延元年 |
海野信濃守幸恒の長男海野小太郎幸明の弟たちは分家して祢津氏(祢津小太郎直家)、望月氏(望月三郎重俊)を起している。 海野氏、望月氏、祢津氏、これらを滋野三家といい、三家は緊密で、 出陣の次第によると海野自ら戦うときは海野幡中、左望月、右祢津となり、望月自ら戦うときは、望月幡中、左海野、右祢津となり、 祢津自ら戦うときは、祢津幡中、左海野、右望月と、三家一体となって外敵に当たったという。 この頃の家紋は海野氏が洲浜や月輪七九曜、結び雁金で、望月氏は丸に七曜または九曜の紋、祢津氏は丸に月であったとされる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康平5年 |
陸奥国の俘囚長安部頼時が叛き、前九年の役が起こる。
この合戦で海野信濃守幸家は80騎の棟梁として源頼義に従い安部頼時討伐に従軍する。 海野幸家には弟下屋幸房がおり、下屋滋野氏の祖とされる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永保3年 | 安部氏の反乱を鎮圧した以後の安部氏の領土は、味方した清原一族が功績により支配することになり、 旧領出羽を合わせて強大になり、その上当主清原武則が鎮守府将軍に任ぜられ、清原氏の勢力はますます拡大。 しかし孫の清原真衡の代になり一族の間に争いが起こり、領域は乱をはじめた。 永保3年(1083年)、陸奥守として赴任してきた源頼義の嫡男源義家はこの争いに介入し、 最初は清原真衡を応援し一応鎮定していた。しかし清原真衡が急死すると、 今度は相手方の清原清衡と清原家衡の間で争いが起こり、源義家は清原清衡方に加勢。 清原家衡を倒し、寛治元年(1087年)9月、乱を平定した。 この乱を後三年の役と称す。 海野信濃守幸勝は180騎の棟梁として 源義家に従い陸奥国の清原清衡討伐に従軍する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保元2年 | 海野小太郎幸直は、海野左衛門尉幸親(海野太郎)、祢津通直(祢津神平道直)、望月廣重(望月広重)ら兄弟たちとともに、 保元の乱において300騎の棟梁として源義朝に属し京に上り参戦。戦功をあげる。 『保元物語』に出てくる「海野太郎(宇野太郎)」と「祢津甚平(祢津神兵)」は海野と祢津に本領を持った土豪の海野幸親と祢津通直のことで、海野氏の名前が史実に出た最初である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治承5年 |
木曾義仲(源義仲)は白鳥河原にて兵を集結挙兵し、
海野幸親の長男海野弥平四郎幸広(海野行広)はこれに応じ、侍大将として、集結した滋野一族をはじめ1000、または2000騎といわれる(『平家物語』により)。
海野幸親が指揮する東信濃、北信濃、南信濃、西上州の軍勢は救援として出兵し、越後国の城助茂の大軍と横田河原で戦う。
木曾義仲と海野氏援兵は横田河原の戦い(横田河原合戦)に大勝する。 木曽義仲に従った者たちは、 木曽豊方、木曽義元、木曽義昌、根井幸親(根ノ井幸親)、樋口兼光(樋口次郎)、 海野幸広(海野弥平四郎行平)、矢田義清(矢田判官代)、今井兼平(今井四郎)、楯親忠(楯六郎)、 手塚光盛(手塚太郎)、足利義房、依田二郎、多胡家包(多胡次郎)、山本義弘、 小諸義兼(小諸太郎)、岡田親義(岡田冠者)、仁科盛直(仁科太郎)、高梨忠直(高梨兵衛)、 落合兼行(落合五郎)、海野幸長(海野大夫坊覚明)、井上光基(井上九郎)、栗田範覚(栗田寺範覚)、 大室直光(大諸太郎)、小林真光(小林二郎)、池田親忠(池田二郎)、茅野光弘(茅野太郎)、 長瀬義数(長瀬重綱)、志賀七郎、新庄則高(新庄次郎左衛門)、矢嶋行忠(矢嶋四郎)、 諏訪豊平(諏訪太郎)、村山義直(村山七郎)、望月秀包(望月太郎)、藤山兼助(藤山左衛門尉)、 河上太郎、祢津泰平(祢津甚平)、三河頼重(三河次郎)、山田重弘(山田次郎)、 平賀盛義(平賀冠者)、中村忠直(中村太郎)、藤原中貞(藤原太郎左衛門)、 富部家俊(富部三郎)、丸子秀資(丸子小忠太)、佐竹秀義(佐竹太郎)、進親直(進次郎)、 保科権八(保科太郎)、更級清澄(更級源吾)、村上信国(村上太郎)、津田三郎、 高山重遠(高山三郎)、入江親貞(入江小次郎)、那和弘澄(名和太郎)、林光平(林太郎)、 松本忠光(松本次郎)、金田茂吉(金田次郎)、桜井行晴(桜井太郎)、高楯光延(高楯次郎)、 津波田三郎、吉田四郎、稲問三郎、泉重満(泉三郎)、東十郎、野尻太郎、 平原景能(平原次郎)、小沢景俊(小沢左平衛)、稲津親忠(稲津新助)、富樫家通(富樫太郎)、 太田次郎らがいる。 木曽義仲上洛の折には謀議に参加し、祐筆として都に慣れない木曽義仲と公家社会との間に立って接点の役目をしていた 海野幸長(海野大夫房覚明)たが、間もなく辞して比叡山にのぼる。 海野幸長(海野大夫房覚明)の去った後の木曽義仲と公家社会との間は急に険悪となり、 木曽義仲の人気は急落する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿永2年 |
5月、木曾義仲は侵攻してきた平維盛の大軍を倶利加羅峠で破る。 7月、都落ちした平家を追って上洛を果たす。 閏10月1日、後白河院の命により平家追討の院宣を受け、平家追討のために西下。備中国に出陣。 海野幸広、矢田義清に率いられた5000余人の木曾義仲軍は、 船500艘に兵7000を乗せて反撃してきた平重衡(平教経)を大将とする平家軍と水島にて海上戦となる。 木曾義仲軍は海戦に慣れていなかったため、 水島にて散々打ち負かされ大敗北を喫し京都へ逃げ帰った。 総大将海野幸広は備中の水島の戦い(備中水島合戦)で木曾義仲が平家に敗北したとき討死した(『源平盛衰記』により)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿永3年/元暦元年 |
正月、木曾義仲は征夷大将軍となり「旭将軍」と称せられた。しかし、それもつかの間で、
源頼朝の代官として京に進撃してきた源範頼・源義経の軍に敗れ、北陸へ落ちる途中、
1月20日、近江国琵琶湖畔粟津(粟津合戦)で討死した。
海野幸親も討死している。 木曾義仲が滅亡した後、木曾義仲の長男木曾義高の死罪処分が決定する。 海野幸親の三男海野幸氏は木曾義高の身に危険が迫ったのでいち早く欺き、木曾義高を逃して身代わりとなった。 程なく木曾義高は討手に捕えられて殺されてしまったが、幸いにも海野幸氏は、 その忠義を源頼朝に褒められて許され、鎌倉御家人に加えられた(『吾妻鏡』により)。 これより海野幸氏は源頼朝の側近として仕えることになり、弓の名手として後年名を上げることになる。 木曽義仲の菩提を弔うべく木曽に帰ってきた海野幸長(大夫房覚明)は柏原寺に木曽義仲公を祀り、 寺名を日照山徳音寺と改める。木曽義仲の霊はここに眠っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文治6年 |
海野幸氏が白鳥神社を太平寺より現在地へ移動させ、居城を古城から太平寺(白鳥台団地)に移す。 海野幸氏は源頼朝の射手として弓始めに参加している。 海野幸長(大夫房覚明)が別所常楽寺を復旧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉時代 | 海野幸氏は曽我十郎祐成と曽我五郎時致兄弟仇討ちの取り鎮めに源頼朝警護役として出陣し、 曽我時致と渡り合い負傷する。 5月、源頼朝が富士の裾野で狩を催したとき、同じ信濃武士である藤沢二郎、望月三郎、祢津二郎らとともに 弓の名手として参加したという(『吾妻鏡』により)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建仁元年 | 海野幸氏は越後国鳥坂城にて城資盛を討つ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建保元年 | 和田義盛が叛き、海野幸氏は出陣して和田義盛を討つ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建保4年 | 建保4年(1216年)10月、海野幸氏の次男海野左衛門尉長氏の名が幕府御家人として見られる(『吾妻鏡』により)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承久3年 | 海野幸氏は執権北條泰時の幕府方の将として承久の乱において 美濃大井戸で参戦する。 北條泰時に従い東山道の大将武田信光の軍に属し出陣。 海野幸氏は50歳。幕府重臣として重要な事項の謀議に参加している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉禄元年 | 海野幸長(大夫房覚明)は71代慈円上人の弟子となり、その後は源空(法然上人)の弟子を経て、 親鸞に従い、親鸞の行状記を記して、子の浄真に授ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文暦元年 | 海野幸長(大夫房覚明)は白鳥庄に康楽寺を建設。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉禎3年 |
8月、海野幸氏は北條泰時の嫡男北條時頼に流鏑馬の故実を指南する。 北條時頼に流鏑馬の故実を指南した時の海野幸氏の年齢は65歳。 鶴岡八幡宮における流鏑馬で騎射の技を披露し、見るものたちは海野氏を「弓馬の宗家だ」と讃えたという。 海野幸氏は天下八名手の一に数えられ、さらに武田信光、小笠原長清、望月重隆とならび 「弓馬四天王」と称されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁治2年 |
仁治2年(1241年)3月、幕府の公式記録『吾妻鏡』によれば、海野幸氏は甲斐国守護であった武田信光と、上野国三原荘(群馬県吾妻郡嬬恋村三原)と信濃国長倉保(軽井沢付近)の境について争論し、
幕府の裁定によって海野幸氏が勝訴しており、すでにこの時期に
海野一族が上野国に進出して三原荘を領有していたこと、
そして甲斐国武田氏と争うほどの一族であったことが注目される。 海野郷の周辺はもとより、遠くは西上州(吾妻郡)、東は小諸、東南は佐久地方、西は四賀村付近まで広がり、 この時期の海野氏の支配地域は、海野氏連合体全体で江戸時代の石高に換算すると、5万石〜7万石程度と推定される(信濃全域で55万石から換算して)。 海野幸長(大夫房覚明)が死去。享年は75歳。海野幸長(大夫房覚明)は『平家物語』の語り手の一人ではないかと推測されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建長2年 | 建長2年(1250年)3月、海野左衛門入道の名が幕府御家人として見られる(『吾妻鏡』により)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文永11年 | フビライ率いる中国(蒙古)、高麗の兵28000が、 壱岐・対馬を侵略の後10月20日には九州博多湾西部の今津付近に上陸し、文永の役が起こる。 将兵よく防戦して勝敗がつかぬため攻撃軍は一旦沖の船に引き上げた。 その晩台風に遭いフビライ軍は多くの船が沈み、多数の将士を失う。残る兵力は戦意を失い敗退していった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘安4年 | フビライの日本侵略の夢は消えず、降伏勧告の使者を日本に送ったが、執権北條時宗は従わず、 使者を鎌倉竜ノ口にて斬り、覚悟の程を示し九州を主体として沿岸の防備をますます堅固にした。 フビライは日本侵略の兵力を金方慶を主将とする蒙古・漢・高麗合流軍40000の東路軍と、 笵文虎の率いる旧南宋軍100000の江南軍を編成して日本に向けた。 弘安4年(1281年)6月6日、東路軍は志賀の島に襲来。待ち受けていた幕府軍と激戦になり勇敢な将士の反撃に侵略軍は上陸を果たせず退き、 江南軍の到着を待った。東路軍は遅れた江南軍と平戸付近で合流し、一挙に博多湾に押し入るべく鷹島付近に移動。 これを察知した日本軍は小舟にて猛攻をかける。 激戦の最中、7月30日から暴風雨が吹き荒れ、翌閏7月1日には来襲軍の船はほとんど壊滅し、笵文虎は士卒を置き去りにして本国へ逃げ帰り、 残された将兵は殺害または捕虜となり、日本軍の大勝利のうちに終わった。これを弘安の役といい、 海野信濃守幸継は、塩田氏に従い出陣している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元弘3年 |
元弘3年(1333年)5月、新田義貞が鎌倉へ出兵。鎌倉幕府軍は金沢貞将、桜田貞国らが迎撃。
5月11日、ついに両軍が衝突。 5月12日、武蔵国久米川(東京都東村山市諏訪町)において、桜田貞国率いる鎌倉幕府勢と新田義貞率いる反幕府勢との間で久米川合戦が行われる。 5月15日、武蔵国多摩川河畔の分倍河原(東京都府中市)において、北條泰家率いる鎌倉幕府勢と新田義貞率いる幕府勢との間で分倍河原合戦が行われる。 一進一退の攻防が5日間におよび、ついに新田義貞は北條軍を破り怒濤のごとく鎌倉に攻め入った。 これらの合戦を総称して小手指ヶ原合戦(小手差原合戦)と呼んでいる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室町時代 |
信濃国は古代以来、東国に属し、東国の西端に位置する。
鎌倉時代には北條氏が守護となり、諏訪氏と滋野氏はその家臣として勢力を伸ばしていた。
滋野氏は諏訪氏に接近し、諏訪社の氏人として同族意識を持つようになる。
このため、宗教色に強く染まることになり、霊界と深く関わるようになっていた。
滋野氏が諏訪氏と行動を共にするようになり、浅間山信仰は諏訪信仰と結びつくようになったのである。
祢津氏が諏訪氏の一族となり、「神平」と名乗るようになったのもこの頃かと思われる。 室町時代になると、小笠原氏は幕府の忠実な与党であったが、 鎌倉府は小笠原氏と対立的な村上氏等を嗾けて、信濃国をその支配下に置こうとしていた。 滋野氏の根拠地東信濃は、幕府と鎌倉府の引っ張り合いになりがちな地となっていく。 海野幸康は滋野一族として諏訪頼重とともに北條時行を奉じて鎌倉を攻略し、 逃げる足利直義軍を追って東海道を攻めあがった。 これは鎌倉執権の北條氏を先代、室町幕府の足利氏を当代と呼んだので、その中間に起きた乱のため、 建武政府に対して起こしたこの乱を後世の職者は中先代の乱と称したという。 海野氏を含む、諏訪氏、滋野氏、北條時行軍は各地で戦果をあげ、守護小笠原貞宗の軍を破り、武蔵国小手指ヶ原で足利軍を追撃(小手指ヶ原合戦)。 7月27日、手越河原の戦い(手越河原合戦)では、 さらに足利直義を三河方面まで敗走させたが、 足利直義救援のため京都より東下した足利尊氏軍は三河国の矢萩(岡崎市)にて足利直義軍と合流し、 8月9日に進撃してきた北條時行軍と橋本(静岡県浜名郡)にて合戦(橋本合戦)、 足利尊氏軍はこれを破り、敗走する北條時行軍を追って、途中小夜の中山(掛川市)でさらに破り(小夜中山合戦)、 14日には府中(静岡市)の合戦(府中合戦)に勝利した。 北條時行軍は続いて高橋縄手、清見ヶ関(清水市)と息つく間もなく攻め立てられ(高橋縄手合戦/清見ヶ関合戦)、 防戦の甲斐もなく敗走する。17日には箱根山(箱根山合戦)、 18日には北條時行軍の最後の陣地相模川にて合戦(相模川合戦)、 ここを最後の場所としてよく防ぐも敵わず、足利尊氏は19日には鎌倉を奪還。 諏訪頼重は自害し、北條時行による鎌倉奪還はわずか20日間。北條氏再興の目的はあえなく挫折してし、夢に終わった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正平7年 |
南北朝時代には、滋野氏や北條氏の残党は南党として、北党の新守護小笠原氏や村上氏と対立する。 足利尊氏の弟足利直義が鎌倉で急死すると、これを契機に 関東や信濃を中心に南朝方と鎌倉の足利尊氏との間に激しい戦いがはじまる。 南朝方は宗良親王を総大将として、諏訪氏および海野氏を棟梁とする滋野一族で、 碓氷峠を通り笛吹峠に陣を敷いた。 神家と記されている諏訪氏、高梨氏、仁科氏、伴野氏(友野氏)、祢津行貞(祢津小二郎)、滋野八郎(繁野八郎)、尾沢八郎(矢沢八郎)らが宗良親王味方をしている(『信濃勤王史』により)。 また上州では新田義貞の子新田義宗、新田義興兄弟が兵を起こして鎌倉を攻めている。 閏2月15日、新田義宗・新田義興ら南朝方の軍勢を国府付近で戦い(武蔵野合戦)、双方相当な被害が出る。 閏2月18日、新田義興ら南朝勢は、鎌倉街道を南下し、にいったん鎌倉を占領。 石浜(東京都台東区)に撤退し勢力の回復をはかり、武蔵国狩野川に布陣した足利尊氏は兵を整えて上州へ北上。 新田義宗は笛吹峠(埼玉県嵐山町)に陣を敷き、宗良親王ら信濃勢や、足利直義派であった上杉憲顕と合流。 足利尊氏は宗良親王と新田義貞軍を分断し、 まず、閏2月20日、金井原(東京都小金井市)および人見原(東京都府中市)にて足利尊氏勢は新田義興軍と合戦を行い新田軍を撃破(金井原合戦/人見原合戦)。 続いて2月28日、笛吹峠に布陣していた宗良親王とは高麗原(埼玉県日高市)・入間河原(埼玉県狭山市)・小手指ヶ原(埼玉県所沢市)で合戦(高麗原合戦/入間河原合戦/小手指ヶ原合戦(笛吹峠合戦))となったが、 足利尊氏勢が勝利し、宗良親王は信濃方面に落ち延び、香坂高宗に庇護され大河原城に滞在 海野幸康は、『群書類従』によれば、宗良親王に従って戦ったが、 足利尊氏軍と戦って大敗し、笛吹峠で戦死する。 『太平記』では祢津行貞(祢津小次郎)の豪勇ぶりが詳しく記載されている。 3月12日、足利尊氏は鎌倉を奪還。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応永7年 |
応永7年(1400年)、足利氏に頼んで宿願の信濃守護を拝命した小笠原長秀であったが、衆目を驚かすばかりの都風のきらびやかな行列を整え、
伊那勢200余騎を従えて川中島を練り歩き、守護所のあった善光寺に入る。
信濃の武士たちが進物を捧げて伺うも、小笠原長秀は尊大でろくな挨拶も返さず、腹に据えかねた各地の豪族たちは、
早速協議のうえ、北信濃の村上氏を旗頭に、高梨氏、島津氏、井上氏、海野氏、祢津氏、仁科氏、香坂氏、諏訪氏、その他の豪族を加えた大連合を組織して、
善光寺から討って出た小笠原長秀勢と横田河原で戦い勝利する。
更埴地域で強大化しつつあった村上満信の当知行地に対する守護小笠原氏の圧力への反発が発端ともいわれている。 つづいて大塔城(長野市篠ノ井)を攻め落とし、小笠原長秀はほうほうの体で京都へ逃げ帰った(『東部町歴史年表』により)。 これを大塔合戦といい、海野幸永、海野幸昌父子は祢津遠光を大将として、 中村弥平四郎、会田氏、岩下氏、大草氏、大井氏、光氏、田沢氏、塔原氏、深井氏、土肥氏、矢島氏らを率いて村上満信に与し、 守護小笠原長秀に反乱し、勝利している。 『大塔物語』には祢津遠光の配下として、桜井氏、別府氏、小田中氏、横尾氏、曲尾氏、実田氏などの武士たちの名も記されており、 「実田」は真田氏のことで、この当時の真田氏は、横尾氏や曲尾氏らと並ぶ山間の小土豪にすぎなかったことが分かる。また「海野宮内少輔幸義、舎弟中村弥平四郎、会田岩下、 大草、飛賀野、田沢、塔原、深井、土肥、矢島以下」と記されている。 なお、大塔合戦では村上満信が国人衆の指導的な役割を果たし、以後大いに勢力を振るい北信濃一帯を制覇したところを見ると、 当時村上氏がいかに強力な名門土豪であったかが窺い知れる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永享10年 | 結城氏朝が関東管領足利持氏の遺子を奉じて挙兵し下総国結城城に拠ったので、 将軍足利義教がこれを討った戦い、いわゆる結城合戦において、 海野幸数ら信濃の将士たちは守護小笠原氏に従い出陣。従軍した将士たちの名は『結城陣番帳』に記されており、 信濃の雄である村上頼清に従って出陣した武将の中に、 真田源太郎、真田源五郎、真田源六郎の名が記されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉吉元年 | 嘉吉元年(1441年)、南朝尹良親王の子良王治良が祖父宗良親王ゆかりの信濃国に入部。 良王治良は望月光経を頼り、日台の古館、王城に拠って大将軍と称した。 高呂城主郷東寺盛寛を管領として兵を募り、海野幸義、海野持幸父子らをはじめ、 祢津貞高、桃井直広、羽川広常、矢沢有光、茂田井経景ら300余騎が応じ、王城を守備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝徳元年 | 海野持幸が海野本郷の諏訪社頭役を勤仕している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寛正6年 | 寛正6年(1465年)12月8日、甲斐国武田信昌と駿河国今川義忠は、将軍足利義政からの 古河公方足利成氏追討の命を受け(『足利家御内書案』により)、信濃念場の野辺山へ軍を進める。 武田信昌、今川義忠連合軍が村上政清軍と対陣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文正元年 | 文正元年(1466年)3月10日、村上政清が武田信昌と対戦(念場野辺山合戦)。 武田信昌は村上政清の武将杵淵下野守と戦う。 多くの戦死者を出して両者とも撤退した(『蔭涼軒日録』により)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応仁元年 |
応仁の乱が起こる。
村上政清との境界争いが原因で合戦となり、海野持幸が戦死。
塩田平までも村上政清に制圧されることとなり、村上氏は戸石城を築城し海野氏を牽制。
海野持幸が討死して以来、村上氏に圧迫され海野氏はしだいに衰亡していき、
西上州の国人衆も海野氏の支配下を離れ、関東管領上杉氏勢力下の箕輪城主長野氏の支配を受けるようになっていく。
海野氏の勢力圏はしだいに狭められ衰亡期といっても過言ではない。
この時期、海野氏の支配圏は海野郷を中心にして、西は芳田や深井周辺、東は祢津の東側一帯の別府氏支配地域まで。
北は鳥居峠付近の西上州境界付近の祢津氏所領まで。南は千曲川付近の小田中氏所領までとされている。
この範囲内での海野氏支配の規模を江戸時代の石高に換算すると、1〜2万石と考えられている。 塩田平を制圧した北信濃村上政清は佐久地方にも侵入。 大井持之を攻め(大井原合戦)、大井氏を破る。 南佐久の伴野氏も大井氏と戦い、大井氏は惨敗。 勢力を維持していた佐久の名門大井氏も衰退していく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応仁2年 | 小県郡をめぐって海野氏幸と村上頼清の戦いが起こった。いわゆる海野大乱である。 かつての大塔合戦では、味方同士であったが、守護小笠原氏の衰退に伴って、 ともに勢力を拡張させていき、所領の境界をめぐって争いが起こったものと思われる。 村上氏が攻勢に出て海野領に侵攻したとされる。 この時点での真田氏の動向は不明であるが、真田郷の洗馬城が戦場になったこともあり、 真田は海野一族との意識からすれば、当然村上氏に対抗したことが予測される。 村上氏が小県郡へ進出し、滋野一族は徐々に圧迫されて、所領を縮小させていく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文明4年 | 文明4年(1472年)4月22日(4月24日)、 大井政朝が信濃佐久郡から甲斐八代郡まで攻めるが、武田信昌に撃退される(『勝山記』により)。 佐久郡の大井氏は、この頃は坂城の村上氏に圧迫されており、国内が乱れている甲斐国へ活路を見出そうとしたのではないかと思われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文明11年 | 文明11年(1479年)8月、佐久郡岩村田の大井政朝が前山城伴野光信と戦って敗れる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文明16年 |
文明16年(1484年)2月27日、村上政清、村上政国父子が大井城を攻略し、暴風のもとで四方に火を放つ。
260年持ちこたえた大井城下を焼け野原とし、佐久の名門大井氏大井政則は村上氏の軍門に降る。
佐久郡の名族大井氏が村上政清によって攻められ没落する。 海野氏も村上氏によって圧迫されていたわけで、佐久郡の大井氏までもが村上氏によって圧されていたとなると、 村上氏の勢力は相当なものだったと予測できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長享元年 |
真田右馬允頼昌が真田幸綱の次男として生れる。
真田頼昌は海野幸棟の娘を娶っている。
海野棟綱の妹婿であり、真田頼昌の長男真田綱吉、次男真田幸隆、三男矢沢頼綱、四男常田隆家、五男鎌原幸定らは
海野棟綱にとっては甥にあたる。 真田頼昌は、一説には矢沢氏を嗣ぎ矢沢頼昌と名のるが、後に真田氏を嗣ぎ真田右馬佐道端と名のったという。 矢沢氏は後に真田頼昌の次男真田頼綱(矢沢頼綱)が嗣いでいる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延徳元年 |
被官の国人衆の領地を除いた海野氏の直轄領地は、
延徳元年(1489年)の『諏訪上社御符札』の古書によれば、
この時期の海野氏の所領は、東は東上田、海善寺、海野本郷、北は小井田、林、
西は樋沢(樋の沢)、房山、踏入、南は千曲川端までとされており、庶子である海善寺氏や太平寺氏の一族を代官として従え、
さらに深井氏、小宮山氏、今井氏、平原氏、岩下氏らを被官としてこれらの地域を支配していたという。
天正10年(1582年)10月に北條氏直が祢津昌綱(祢津信光)に宛てた文書(『禰津文書』)には、
徳川氏から北條氏へ寝返れば、海野氏の旧領4000貫を宛て行うと申し送っていることが明らかとなっている。
この文書からも海野氏の領地の規模が推測でき、4000貫を石高に換算すると(一貫二石四斗七升)、1〜2万石と予測できる。
永正元年
海野幸棟は文亀3年(1503年)に夫人禅量大禅尼が没したため、夫人のため興善寺の開基となる。 | 大庭地籍の耕雲寺で発見された石塔群の五輪塔から曲尾氏の形跡が見られる。
永正7年
真田綱吉が真田頼昌の嫡男として生れる。 |
永正10年
真田幸隆(真田幸綱)が真田頼昌の次男として生れる。
真田幸隆は伯父海野棟綱から海野姓を許されたともいわれているが、定かではない。
海野家当主の海野幸義とは従兄弟の関係にある。
おそらく真田幸隆が武田氏仕官後に滋野一族の調略のために海野氏系図を改竄し自らが滋野一族の嫡流であることをこじつけたのだろうともいわれている。
いずれにしても、真田幸隆が滋野一族を次次と家臣に加えていき、武田晴信の信濃侵攻に大きな功をたてている。 |
永正15年
真田頼綱(矢沢頼綱)が真田頼昌の三男として生れる。
父真田頼昌が矢沢氏に入っていたという説もあり、真田頼昌死後に矢沢氏を嗣ぎ、矢沢頼綱と名のっている。 |
永正16年
9月、武田信虎が信濃国佐久郡平賀城を攻める(平賀合戦/佐久侵攻戦)。村上顕国、村上義清父子が佐久衆の求めに応じ出陣。
村上義清の初陣とされ、村上勢は8000の兵を率いて小諸城に着陣。
小諸城主小諸光政(大井伊賀守)父子が城外に出て村上顕国、村上義清父子を出迎えている。
多勢の出現を知り武田信虎は平賀周辺に火を放って帰国したという。
|
永正17年
真田隆家(常田隆家)が真田頼昌の四男として生れる。
常田に住み(常田氏を嗣ぎ)、常田隆家と名のっている。兄真田幸隆を補佐し、上野侵攻戦などに活躍する。 |
大永元年
真田幸定(鎌原幸定)が真田頼昌の五男として生れる。
一族鎌原氏に養子として入り、鎌原幸定と名のっている。鎌原氏への人質の意味もあったとする説もあるが、
いずれにしても兄真田幸隆が武田氏に仕えてのちは鎌原氏も武田氏に与すことになり、兄真田幸隆を補佐し、上野侵攻戦などに活躍する。 |
大永2年
8月、武田信虎が佐久郡に侵攻し大井城を攻撃。
村上義清は大井城主大井忠重の要請を受けて出陣。
大井原で戦い(大井原合戦/佐久侵攻戦)、武田信虎は250余の首級を討ちとられ、敗走している。 | 10月、村上義清は勢いにのって平賀源心斎(大井成頼)の求めに応じ逆に甲斐若神子へ出兵(若神子合戦)。 望月昌頼も村上義清に従軍している。 しかしこのときは武田信虎の重臣馬場虎貞が迎撃。村上義清は敗走している。
大永3年
大永3年(1523年)3月15日、真田頼昌(真田右馬佐道端)が死去。享年37歳。真田道端大禅定門一翁宗心大居士。 |
大永4年
海野幸棟が死去。戸石要台寺(陽泰寺)に墓所がある。 | 海野棟綱が高野山蓮華定院宛ての宿坊定書に署判している。
大永7年
信濃佐久郡で大井氏と伴野氏が激戦。 | 6月3日、武田信虎が伴野貞慶を救援するため信濃佐久へ出陣(伴野合戦)。 大井氏らと対陣し、和睦を成立させると武田信虎は善光寺に参詣して帰還した(『勝山記』により)。
享禄元年
8月、神戸・堺川の戦い(神戸合戦・堺川合戦)で武田信虎は諏訪氏に敗れる。
飫富虎昌らが諏訪方に味方したとされている。 |
享禄3年
真田幸隆は羽尾幸世の娘羽尾殿を娶っている。
しかしすぐに死別したという。 |
天文元年
村上義清が家臣楽巌寺雅方、依田新左衛門、布下政朝(布下仁兵衛)らに戸石城を築城させる。
のちに、武田晴信が苦渋をなめることになる難攻不落の名城となる。 |
天文4年
武田信虎は諏訪氏と和睦する。 | 真田綱重が真田綱吉の長男として生れる。 真田綱重は萩原姓萩原綱重を名のった。
天文5年
11月、武田信虎が佐久郡へ出兵する。海ノ口城城代の平賀源心斎(大井成頼)が迎撃するが、武田晴信の活躍により
海ノ口城が陥落したという。
武田晴信の初陣の戦いといわれている。
平賀源心斎は平賀成頼(大井成頼)というのが本名であり、平賀城主である。
当時は大井氏は村上氏に圧され村上氏に従っていたという。また佐久郡をめぐって村上氏と武田氏の争いもあったということから、
平賀源心斎成頼も村上氏配下として海ノ口城の城代をつとめていたとみるべきだろう。
つまりこの(海ノ口城合戦/佐久侵攻戦)は武田氏と村上氏との戦いということになる。
|
天文6年
真田信綱が真田幸隆の嫡男として生れる(『信綱寺殿御事蹟稿』により)。 | 真田信綱の母は河原隆正の妹河原殿。 真田信幸の代に沼田真田家臣の加沢平次左衛門が記した『加沢記』によれば、 真田幸隆の初婚は羽尾幸世の娘とあるが、死別したという。
天文8年
武田信虎が飫富虎昌に信濃佐久へ侵攻させる。
村上義清と飫富虎昌の戦いが繰り広げられ、飫富虎昌が葛尾城まで攻めのぼったともいわれている(佐久侵攻戦)。 |
天文9年
天文9年(1540年)2月、
村上義清麾下の清野氏、高梨氏、井上氏、隅田氏らが2500余の軍勢で佐久郡から甲信国境を越えて侵入し、
八ヶ岳山麓の小荒間まで進攻し、近郷に放火するなど乱暴を働き、甲州八ヶ岳山麓の小荒間(北巨摩郡長坂町小泉)で合戦(小荒間合戦)がおこる。
望月盛昌も村上義清に従軍している。
多田満頼がみごとな夜襲戦の采配をふるって計略によって村上軍を迎撃している。 | 4月、武田信虎の佐久郡侵攻が本格的になり、大攻勢と発展していく(佐久侵攻戦)。 武田信虎は板垣信方に命じて佐久郡臼田城、入沢城など10数城を攻略させ、前山城を築いて在陣している(『塩山向岳禅庵小年代記(塩山向嶽禅庵小年代記)』『勝山記』により)。 5月、武田信虎は板垣信方に佐久郡への出兵を命じ、一日に36城を陥落させる。 村上義清も反撃に出て、楽巌寺満氏(楽岩寺光氏)が日向昌時(日向大和守)や長坂虎房(長坂釣閑斎)を敗走させる。 武田軍の援軍が到着するまで海尻城代の上原昌辰が猛攻を必死にしのいでいる。 武田信虎は村上氏と一進一退の攻防を繰り広げながらも村上氏を圧し、佐久郡をほぼ制圧。 武田信虎の次なる標的は関東管領上杉憲政に与する滋野一族となる。上杉憲政は武田信虎にとっても村上義清にとっても共通の敵であり、 武田信虎は同盟関係にあった諏訪氏および小県郡に進出を意図していた村上氏に働きかける。 真田頼昌の妻(海野幸棟の娘で海野棟綱の妹/真田綱吉や真田幸隆、矢沢頼綱の母)は天文9年(1540年)4月26日に没したとされる。
天文10年
5月、武田信虎が村上義清と諏訪頼重を誘って、東信濃の海野一族を討った。 | 武田氏とは敵対していた村上氏であったが村上氏にとっても目の上のたんこぶであった滋野一族への討伐であったため 武田氏と諏訪氏に加わり、 武田氏・諏訪氏・村上氏といった連合軍が滋野一族を襲い、ひとたまりもなく海野氏は滅亡。 武田信虎、村上義清、諏訪頼重ともに共通の敵は上野国の上杉憲政であって、 上杉憲政と村上義清の戦いでも、 また上杉憲政と武田信虎の戦いでも、必ず上杉方に与していた海野氏は 上野守護を世襲した関東管領上杉憲政の被官的立場をとって領土の保全につとめてきた。 海野氏は上杉憲政を後ろ楯として対抗しようとしていたのだ。 衰退していたとはいえ滋野一族の力は侮り難く、武田氏や村上氏にとって邪魔者以外の何者でもなかった。 諏訪頼重は立場を少し違えていて、後に上杉憲政と和睦したためにそれを口実に武田晴信に 攻め滅ぼされたほどで、滋野一族とも深い関わりあいをもち、 縁戚関係も小県地方や佐久地方には多く、祢津氏や矢沢氏なども縁戚関係にあった。 なぜ諏訪頼重が村上義清や武田信虎に与したのかは定かではないが、 諏訪頼重は依田窪へ出陣。武田信虎は佐久地方へ出陣。 武田信虎の軍師駒井高白斎の記した『高白斎記』には「天文10年(1541年)5月25日、海野平破り、 村上義清、諏訪頼重両将出陣」とのみ記されており、 また『諏訪神使御頭之日記』には「この年の5月13日、諏訪頼重、武田信虎へ合力のため海野へ出張す。 同じく村上義清殿三大将同心にて尾野山攻め落とされ候」と記されている。 「合力」あるいは「同心」という程度の表現しか残されていないので、海野を攻める利が、三者とも自己の領地拡大という利につながっていたためであろうと考えられる。 いずれにしても、この戦い(海野平合戦)で海野氏は滅亡し、 海野棟綱の嫡男海野幸義は神川河畔での戦いで討死する。 『真田御武功記』には「真田弾正忠幸隆、雑説に海野左京大夫幸義戦死のとき、すでに討死と思い究めたるところに、 神女来たりて、鉾を逆さまに持ち“宜しく此の鉾をもって敵陣を破り、此処を遁れ出て時を待つべし。 末はめでたからん。妾は白鳥明神の御使なり”とて鉾をば真田幸隆に渡して行方知れずなりたもう。 異端疑うべからずとて、一門郎徒その他与力同心、真丸に引きまとって、殊に大勢囲みたる方の真中へ突きて蒐りたまひば、 敵勢ひらき靡き、敢へてつき慕い来らざれば、足を乱さず静かに立ち退きたまうなりと」と記されている。 真田幸隆は海野棟綱とともに上州へ逃亡。 真田幸隆は上州へ逃れる際、祖先の墓が敵に辱められるのを恐れて破壊する。 海野棟綱の家老深井棟広は真田郷に住居していた紀州高野山宿坊の蓮華定院宛に「(上略)…御書中のごとく、不慮の儀をもって当国上州へ海野棟綱罷り除かれ、 山内上杉憲政殿様へ本意の儀頼み奉られ候間、急度還住いたさるべき由存ずるばかりに候。…(下略)」と書状を送っている(『上田小県誌』により)。 祢津氏と矢沢氏は諏訪明神の神氏ということで降伏を許された。望月氏は村上氏に与していたためかこのときには攻められていない。 武田信虎は嫡男武田晴信に追われる。 7月、関東管領上杉憲政は、海野棟綱の乞いにより村上義清を攻めるため佐久郡、小県郡に出兵。 西上野一帯、吾妻、碓氷、甘楽などの豪族たちを配下とする箕輪城主長野業政(長野信濃守)を総大将とし、 鷹留城主長野業通(長野弾正忠)、安中忠成(安中左近太夫)、沼田景康(沼田上野介)らが上州勢を率いて佐久郡へ出兵したというが、佐久郡の大井氏、平賀氏、内山氏、志賀氏ら諸氏は戦わずに降伏。 『神使御頭之日記』によれば上杉軍の出陣について「7月、関東衆3000騎計にて佐久海野へ働候…(後略)」とあり、かなりの大軍であったことが想定される。 箕輪城を出発した上州勢は、安中から富岡に入り、下仁田をへて内山峠から佐久郡に入ったという。 碓氷峠には安中城や松枝城があり、甘楽郡には岡本城、小幡城、国峯城があり、それぞれの城主は長野業政の娘婿として箕輪衆の一翼を担っていた。 内山峠の直下荒船神社で宿営となっている。 内山城には大井貞清(内山左衛門尉)がおり、志賀城には志賀清繁(笠原清繁)がいる。 岩尾城には大井弾正(岩尾弾正)、そして望月城には望月盛昌がいる。 芦田城主芦田信守は諏訪頼重を頼り城を捨てているが、村上氏に与していた佐久郡の豪族はほとんどが上杉氏に忠誠を誓ったという。 羽尾幸全、海野棟綱、真田幸隆らも参陣していたと思われる。念願の小県郡への復帰であった。 しかし長野業政は長窪へ出てきた諏訪頼重と和睦し、関東へ帰還。 海野棟綱や真田幸隆の夢は潰えてしまった。 このことにより、真田幸隆は関東管領上杉氏を見限り出奔したのではないかとされている。
天文11年
7月、武田晴信は妹婿の諏訪頼重を攻め滅ぼし、
諏訪郡を占領する。さらに佐久方面への侵攻を再開した。
12月、祢津元直の娘(祢津姫)が武田晴信の側室として嫁いだ。 |
天文12年
真田幸隆は武田晴信に仕える。
真田幸隆は佐久郡岩尾城代となり、信州先方衆として活躍を始める。
武田晴信は小県郡長窪城の大井貞隆を攻め捕らえる(長窪城合戦)。
ついで望月一族を成敗する。 | 6月、真田昌輝が真田幸隆の次男として生れる。
天文14年
真田幸隆は小県郡の松尾城に復帰する。 |
天文15年
5月、武田晴信は佐久郡内山城の大井貞清を攻め滅ぼす(内山城合戦)。
武田晴信はさらに佐久郡志賀城や小田井原城を攻略する。
真田幸隆も各地を転戦。 |
天文16年
8月、武田晴信が志賀城(笠原山城)の志賀清繁(笠原清繁)を攻める(志賀城合戦)。
上野国から上杉憲政の援軍が来襲するが、小田井原で迎え撃つ(小田井原合戦)。
武田方は板垣信方を大将として、
飫富虎昌、上原昌辰とともに真田幸隆が参戦して勝利する。 | 真田昌幸が真田幸隆の三男として生れる。 真田信尹が真田幸隆の四男として生れる。
天文17年
真田幸隆は、武田晴信の家臣として上田原で村上義清と戦う。
この戦(上田原合戦)で武田方は、板垣信方や甘利虎泰などの重臣を戦死で失っている。 | 2月22日、村上義清は上野国高山(安中)の小領主小林氏に佐久郡の知行を条件に援軍を要請。 すでに板垣信方ほかを討取り、武田方の敗北は時間の問題だと伝えている。
天文18年
7月、小笠原長時が武田方を急襲したが、武田晴信は迎え撃った(塩尻峠合戦)。 | 3月、真田幸隆は望月一族を懐柔した。 望月源三郎、望月新六郎が武田氏に服属し、真田幸隆は所領安堵の朱印状を望月源三郎に伝達した。 真田幸隆の活躍が確実な文献に見える最初である。 真田幸隆の工作に応じて蘆田依田氏(依田新左衛門)、伴野氏らも武田方に降る。 4月、武田晴信が佐久郡春日城を攻略。 9月、武田晴信が佐久郡前山城を攻略。佐久郡平原城を焼く。真田幸隆も参戦している。
天文19年
8月、武田晴信は大兵を率いて村上氏の戸石城を囲む。
10月、真田幸隆は村上氏に属する川中島平の須田氏、寺尾氏、清野氏、春原(須野原)氏らを味方にすることに成功。
村上義清は高梨政頼と手を組み、武田に寝返った清野氏の寺尾城を攻める。
清野氏からの報せに驚いた真田幸隆は、武田晴信に急報し、自らは寺尾城救援に赴く。 | 11月1日、攻囲1ヶ月に及んだが、落城させることができず、囲みを解いて退却した(戸石崩れ)。 真田幸隆は善光寺平へ進んで村上義清の背後を撹乱していたが、 急遽、武田晴信の本陣へ帰り、情況の急変を告げた。 北信濃の反乱を鎮めた村上義清が、全力を奮って戸石城の救援に来るという報告だったらしい。 攻城が失敗しての退却は極めて危険であり、戸石城攻めは完全に失敗であったが、 武田晴信はギリギリの機を逃さず戦場を離脱したのである。 これは退却の最後のチャンスを生かしたものであり、真田幸隆の献策が与って力があったことは疑いない。 真田幸隆は、武田晴信より諏訪形1000貫文の地を与えられる。
天文20年
5月26日、真田幸隆は戸石城を不意を襲って乗っ取る。
真田幸隆の嫡男真田信綱が従軍し一番手柄を立てている。華々しい初陣である。 | 7月25日、武田晴信が信濃国に出陣する旨を飯富虎昌が真田幸隆に連絡する。 これは飯富虎昌と上原昌辰宛ての武田晴信の書状であり、 武田晴信が佐久郡、小県郡へ出馬することを伝えた後、 「尚、この趣、真田方へ物語り有るべく候」とあって、 佐久郡小諸城主飯富虎昌、内山城主上原昌辰と同列に扱っていることにより、 真田幸隆の武田家臣としての地位が固まったことが明らかである。
天文21年
真田幸隆、真田信綱父子が南安曇郡小岩岳城攻略の戦いに出陣。 |
天文22年
4月9日、宿敵村上義清は武田方によって葛尾城を攻落され、
長尾景虎を頼って越後へ亡命している。これにより、川中島合戦が始まることになる。
ここでも真田幸隆は大須賀氏を調略しており、真田幸隆の活躍が大きかったことが窺える。
真田幸隆は戸石城の普請の実務担当をつとめた。 | 8月10日、真田昌幸を人質として甲府へ送る。 代わりに真田幸隆は、武田晴信から上田秋和の350貫の地を与えられる。 真田昌幸が奥近習衆(小姓)に出仕した頃、曽根総次郎、曽根与一、金丸平八郎(土屋昌恒)、三枝勘解由、三枝新十郎含めた6名があげられる。
弘治2年
真田幸隆は埴科郡東條の雨飾城を攻め落とし、城将となる。 |
永禄3年
真田幸隆を通じて海野一族が武田晴信に随順。
海野城築城に真田幸隆も助力する。 |
永禄4年
5月、真田幸隆は西上野に出陣。
9月21日、真田幸隆・真田信綱父子、川中島合戦に参戦。
武田信玄(武田晴信)と上杉謙信(長尾景虎)の一騎撃ちとして伝えられる。
真田幸隆・真田信綱父子は、妻女山を攻める。
斎藤憲広によって鎌原城を攻め落とされ、羽尾幸全が斎藤方として城代となる。
真田幸隆は甘利昌忠とともに鎌原城を奪還する。 |
永禄5年
6月15日、真田幸隆・真田信綱父子は四阿山奥宮社殿を修理した。
四阿山奥宮社殿扉に真田幸綱(真田幸隆)の名が見られる。
真田信綱が連署していることで、嫡男として家督継承者としての立場を明らかにしている。 |
永禄6年
3月、三原荘をめぐって鎌原氏と羽尾氏の争いが再燃する。 | 9月、斎藤憲広は越後上杉家の後ろ盾により長野原城へ進軍。 常田隆家が城代として守っていたが落城(長野原合戦)。 海野棟綱は羽尾氏方の武将として常田隆家と戦う。 真田幸隆は岩櫃城を攻めていたが、戦局は思わしくなく和議を余儀なくされる。 羽尾幸光と羽尾輝幸兄弟が武田方に内応する。 真田幸隆は羽尾幸光・羽尾輝幸兄弟の助力により斎藤実憲を調略する。 10月13日、真田幸隆は上野国吾妻郡の岩櫃城を攻略する。 岩櫃城を鎌原幸重と湯本善太夫に城代として任せる。
永禄7年
3月、武田晴信は海野氏・祢津氏・真田氏らに上野在陣を命じる。
真田幸隆は常田隆家や小草孫左衛門、海野業吉らとともに、
将として上野長野原に出陣し、
海野氏・祢津氏らとともに上野国に在陣。計略に努める。
真田一徳斎(真田幸隆)の号の初見。 |
永禄8年
11月、斎藤憲広の家老である嶽山城主池田重安が城を脱出して真田幸隆に降る。
真田幸隆は嶽山城を攻略する。真田幸隆が吾妻郡代となる。
吾妻衆への感状や知行宛行状には真田幸隆により行われ、
それを受けて武田方の窓口は甘利昌忠が行っている。 |
永禄9年
羽尾幸光と羽尾輝幸兄弟が岩櫃城代となり、吾妻衆70騎の与力と城を守る。
武田晴信が嫡男武田義信の謀反の疑いありとして、自害を命じる。
このとき武田晴信は家臣団の動揺を防ぐためにほぼ全領域の家臣団から起請文を徴収した。
この中で真田氏に関係ある地域のものは、
小県郡では、室賀信俊、海野幸貞、祢津政直、祢津直吉、望月信雅、
依田信守(依田信盛)、小泉一族。
吾妻領では、浦野幸次、海野衆では真田綱吉らの名前がみえる。 | 真田信幸が武藤喜兵衛の長男として生れる。 武田晴信は上野箕輪城を攻略。
永禄10年
永禄10年(1567年)3月6日、真田幸隆は上杉一族長尾憲景が籠る白井城を攻略(白井城合戦)する。
白井城攻略に関しては永禄8年から元亀3年までの間で諸説はあるが、
11月23日白井城代を勤めていた祢津政直宛に武田晴信より知行が宛行われている。 | 8月、武田領の家臣団が武田晴信に提出した起請文には海野氏関係として、海野幸貞(海野三河守)の単独のもの、 海野直幸(海野信濃守)、海野幸忠(海野伊勢守)、海野信盛(海野平八郎)の連名のもの、 さらに「海野被官」として桑名氏、塔原氏ほか5名連記のものと、「海野衆」として真田綱吉(真田幸隆の兄)、 神尾房友ほか12名連記のものがある。海野衆の中には海野幸義の嫡男海野業吉(海野左馬允)の名も見えている。 12月、駿河へ侵攻を開始。真田信綱、真田昌輝兄弟は武田軍先鋒として、 山縣昌景や馬場信房らとともに富士川沿いに南下。真田信綱、真田昌輝は信濃先方衆であるが、 真田幸隆に代わって出陣したものと考えられる。先陣を務めるのは部門の名誉であり、合戦巧者の武将が任命される慣わしでもあった。伊豆韮山の戦いにも従軍している。 真田幸村が武藤喜兵衛の次男として生れる。
永禄12年
武田晴信が駿河蒲原城を陥れ、その旨を真田幸隆・真田信綱父子に知らせる。
9月10日、武田晴信は北條氏邦の鉢形城を包囲。
だが容易には抜けぬため南下して滝山城を囲む。
滝山城の城将は北條氏照。真田信綱、真田昌輝兄弟は工藤祐長(内藤昌豊)と小田原筋を受け持った。
しかしこの城も防備堅固で降陥できず、武田晴信は小田原を目指す。
真田信綱、真田昌輝兄弟は、山縣昌景隊、小幡隊とともに本隊の相模川渡河を警固し、
小田原までの殿軍をつとめる。 | 10月1日、武田晴信は相模北條家の小田原城を攻囲する。撤退において合戦(三増峠合戦)となる。 真田信綱、真田昌輝兄弟は遊軍として山縣隊、小幡隊とともに峠を西に進む。 馬場隊の検使武藤喜兵衛(真田昌幸)が一番槍をあわせるが、中央隊の戦いは熾烈をきわめ、 殿軍の浅利右馬助ら多くの兵が討死し、左右隊によって危機を脱していた。 この小田原城包囲戦で真田昌輝は、北条氏照勢を破るなどの軍功を上げている。
元亀3年
三方ヶ原で武田晴信は徳川家康を破る(三方ヶ原合戦)。
真田信綱、真田昌輝が出陣している。 | 武田晴信は川中島地方からの逃亡者の逮捕を、 小県の諸領主、祢津松鴎軒(祢津常安斎政直)・真田信綱・室賀大和入道・浦野源一郎・ 小泉昌宗らに命じる。 3月、真田幸隆は上野白井城を攻め、計略で落とす。 それを賞した武田晴信は、箕輪城に在城している高坂弾正昌信(春日虎綱)の指示を受けるよう命じる。
天正元年
3月、白井城が上杉方に奪われる。真田幸隆は上野にて上杉軍と戦う。 | 4月12日、武田晴信が伊那郡駒場で没する。
天正2年
5月19日、真田幸隆は武田晴信の死に後れること1年、戸石城で病死する。
享年62歳。真田信綱が家督を継ぐ。 |
天正3年
5月21日、武田勝頼が織田信長・徳川家康連合軍に大敗(長篠合戦)。
真田信綱、真田昌輝がともに戦死する。
真田信綱は享年39歳、真田昌輝は享年33歳。真田信綱の首は、徳川家の渡辺政綱という武将が挙げたという。
真田信綱の法名は信綱寺殿大室道也大居士。信綱禅寺に葬られている。
真田昌輝の法名は風山良薫大禅定門。信綱寺に葬られている。 | 三男武藤喜兵衛が本姓の真田昌幸に復して真田家を嗣ぐ。
天正4年
3月、真田昌幸は高野山蓮華定院に、宿坊に関する書状を発する。 | 4月、矢沢頼綱が沼田城に攻撃を加える。武田勝頼はこの報を耳にし、助勢を命じる。 5月23日、真田昌幸は沼田城に入城していた羽尾幸光らに武田勝頼の指示により軍令を発する。 9月10日、武田勝頼は女淵城主新井図書の動向を真田昌幸に探らせる。
天正6年
3月、越後の上杉謙信(長尾景虎)が死んで、養子の間に相続争い(御館の乱)が起こり、
越後国が乱れると、上州方面への上杉氏の圧力が弱まってたのに乗じて、
真田昌幸は上州への経略を進める。 |
天正7年
3月17日、真田昌幸は上野国吾妻郡の地侍羽尾幸光らに
上野中山城と尻高城を奪取したと報じる。 |
天正8年
4月26日、真田昌幸は沼田城潜入を田村角内に命じ、籾50俵を与える。
5月4日、上野国猿ヶ京三ノ曲輪に放火した中沢半右衛門に荒牧10貫文を宛行う。
真田昌幸は上州名胡桃城と小川城を攻略する。
沼田城将藤田信吉が武田方に降る。
真田昌幸はついに要衝沼田城の招降に成功した。 | 5月23日、真田昌幸は沼田・吾妻に法度を発する。 武田晴信亡き後、武田の勢力は日々に縮まりつつあったことから、 これは真田昌幸の力によるもので、真田昌幸が自立の方向に歩み始めていることを物語っている。
天正9年
7月10日、真田昌幸は内応した須田新左衛門に南雲20貫文を与え、また屋敷地などを安堵。
岩櫃城代をつとめる羽尾幸光と羽尾輝幸の兄弟が、相模北條家重臣の猪俣邦憲の誘いに応じて
真田昌幸に反旗を翻す。
矢沢頼綱や吾妻衆の活躍により事なきを得たが、真田昌幸の沼田領掌握が不安定なものであったことをしめしている。
真田昌幸は沼田城に矢沢頼綱を城代として入れ、
岩櫃城は池田氏、鎌原氏、湯本氏の3名に預けて守りの体制を強化した。 |
天正10年
武田氏滅亡の時、真田昌幸は武田勝頼を上州岩櫃城に迎えようとしたが、
武田勝頼は「真田は外様だから信用できぬ」と言う小山田信茂の居城岩殿城へ
入ろうとしたが、小山田信茂の謀反によって討ちとられた。
ただし、これは『甲陽軍鑑』の伝えるところで、事実に反しているともいわれる。
2月、真田昌幸は武蔵鉢形城主北條氏邦を通じて北條氏直と連絡をとっており、
武田と共倒れになるつもりなどは全くなかった、というのが真相のようだ。 | 3月4日、真田昌幸は2500騎を率いて岩櫃城を立ち、戸石城へ入る。 祢津氏、室賀氏により高遠城の陥落と織田勢が今にも攻めてくるとの報せを受ける。 真田氏は一族とともに守りを固める。 3月11日、武田勝頼一族が天目山で自刃。 4月8日、真田昌幸は織田信長に馬を贈って臣従の意を表明した。 6月2日、織田信長が殺されると、上杉景勝(長尾景勝)に従う。 7月、北條氏直は東信濃に侵入、北信濃に侵入した上杉景勝(長尾景勝)と対陣したが、 この時は真田昌幸は蘆田氏、高坂氏(香坂氏)、小笠原氏ら信濃国衆と談合して北條氏に属している。 9月、真田昌幸は弟加津野信尹(真田信尹)らの勧めで、徳川家康に属す。 9月19日、徳川家康が屋代秀正に真田昌幸が徳川方に身を投じたことを報じる。 10月14日、真田昌幸は羽尾城に湯本三郎右衛門を城代に任命し、普請を命じる。 10月22日、真田昌幸は正式に相模北條家から離脱。報復の為に北條氏直が信濃国佐久郡と上野国吾妻郡へ 兵を進める。 10月、徳川・北條の和議が成立し、真田昌幸は独立の地位を確保した。
天正11年
1月、小県郡依田窪の丸子氏を中心とする地侍が徳川家に反発。
真田昌幸、真田信尹兄弟がその制圧に向っている(丸子合戦)。 | 2月22日、佐久郡岩尾城の大井氏を依田信蕃が攻める。 しかし攻略に失敗し、依田信蕃、依田信幸兄弟が戦死してしまう。 真田昌幸は千曲川の河岸段丘の上(尼ヶ淵)に上田城を築いた。 3月、真田昌幸は、埴科郡虚空蔵山にて上杉景勝軍を破る。 3月14日、上杉家に属していた更科郡屋代勝永が徳川家に従う。 4月、屋代勝永の兄室賀満俊も徳川家に従う。 9月29日、徳川家を離反し北條家についていた祢津信光(祢津昌綱)が再び徳川家に従い、 本領安堵状を受けている。 12月25日、真田昌幸は不作の報を受けて年貢を減免。
天正12年
真田昌幸は、吾妻郡の一場右京亮に問屋業を許可する。 | 真田昌幸は小県郡で対立していた室賀正俊を上田城に招いて謀殺する。 小牧長久手合戦で徳川軍は全軍結集されており、 手薄になった小県郡の統一と掌握を進めた真田家に対抗できる在地領主は祢津家を残すのみとなった。 真田昌幸は徳川家康が新知宛状の約束を実行していないことと、まず沼田領の譲渡が先との条件を不満として、 徳川家に従うべきとの重臣の意見を退けたという。 真田昌幸は徳川家康との対決を決断したわけであり、当然、北條家との対立激化も予想されている。 他大名との関係で独立した外交権を有していたことなどを指標とするならば、 すでにこの段階の真田家は大名化を遂げていたと見るべきであろう。
天正13年
5月8日、真田昌幸の調略により上杉家を離反した高井郡福島城の須田信正が、
上杉景勝の命により川中島海津城代の上條氏に成敗される。 | 6月12日、海津城代には上條氏に替わって須田満親がなる。 7月、真田昌幸は上杉景勝に和を乞い、徳川家と手を切る。 次男真田幸村と従弟矢沢頼康を人質として上杉方(春日山城)へ送っている。 7月15日、上杉景勝は起請文で真田昌幸に、 沼田・吾妻・小県などの他に、屋代一跡(屋代秀正の旧領)も給付する、としている。 この安堵状から真田幸村が屋代氏の旧領を上杉景勝から与えられ、 既に独自の家臣を持とうとしていた様を知ることができる。 なお、屋代旧臣諏訪久三の本領をそのまま安堵するとしている。 上杉景勝は海津城代の須田満親を上田城近くの地蔵峠まで兵を進め、 徳川勢を牽制する。 閏8月2日、徳川家康は鳥居元忠、平岩親吉、大久保忠世らに信濃の諸将を付し、 遭わせて7000余の兵を派して上田城を攻めるが、1300余の戦死者を出して敗れた(第一次上田合戦)。 支城戸石城には長男真田信幸が籠る。 真田昌幸・真田信幸父子は国分寺で徳川軍を破り、天下に勇名を轟かす。 徳川勢はなおしばらく付近に滞陣して井伊直政の5000余の援軍で支城丸子城を攻めたが、 これも落とせなかった。 9月、北條氏邦と北條氏照を大将に北條勢が沼田城へ3万8000の軍勢で攻める。 矢沢頼綱と沼田衆は上田からの援軍は望めず、籠城する。 9月29日、北條勢は真田方の守りの固さに落城させることが出来ずに退陣している。 11月13日、石川数正が出奔したため、信州出陣の諸将は呼び返された。 木曾義昌や小笠原貞慶らも徳川家を離反し豊臣方についている。 小笠原氏が伊那郡に乱入し保科氏と衝突している。
天正14年
7月、徳川家康が真田昌幸討伐のため駿河国まで出馬するが、豊臣秀吉の斡旋で延引となる。 | それまで真田昌幸に向かって、徳川家康を討つと広言していた豊臣秀吉が、 徳川家康と和睦し、真田昌幸に徳川家康に臣従するよう命じた。 9月7日、真田昌幸は中山城攻めに参加した林弾左衛門に、割田新兵衛の旧領を与える。 9月、徳川家康の真田討伐は中止。 11月、真田昌幸は止む無く豊臣秀吉の命に従い、長男真田信幸を徳川家康に出仕させた。 人質の意味である。
天正15年
真田昌幸は駿府国で徳川家康に謁見する。 |
天正17年
11月、真田信幸は豊臣秀吉の命で沼田城を北條氏直に渡す。
名胡桃城は真田氏に残すものとなった。 | 11月3日、真田昌幸は、上野国吾妻や沼田城付近の祢津幸直、塚本肥前守、折田軍兵衛 らの知行を信濃国内に切り換える。 11月12日、真田昌幸は上野国名胡桃城に鉄砲15挺を入れる。 北條氏直の家臣猪俣邦憲が名胡桃城を奪取し、鈴木主水重則が討死する。 豊臣秀吉は、北條氏討伐の命令を下す。 真田幸村は豊臣秀吉に従って小田原攻めに加わり華々しい高名を稼ぐ。
文禄元年
真田幸村は豊臣秀吉の馬廻りとして名護屋に在陣。
豊臣家の奉行大谷吉継の面倒を受けるようになる。
名護屋からの帰陣後には真田昌幸、真田信幸は、豊臣秀吉から京都伏見城の築城普請役を命じられる。
|
文禄2年
8月、豊臣秀頼の誕生によって、一応は完成していた伏見城にさらに拡張工事を再開。
12月7日、一旦は普請役を免除されていた真田信幸だが、石田三成ら三奉行に上京するように要請を受けている。
真田昌幸のほか真田信幸、真田信繁(真田幸村)の三名に命じられたものという。
さらに真田昌幸は普請の最終段階で急に木曽材の運搬役を豊臣秀吉から申し付けられている。 | 真田幸隆の妻河原殿が死去。「松代長国寺」の過去帳に 「喜山理慶大姉、文禄2年(1593年)8月11日卒、真田弾正忠幸隆入道之妻」とある。
文禄3年
11月2日、相次ぐ軍役や労役の賞として豊臣秀吉の推挙によって、
真田信幸に従五位下伊豆守と豊臣姓が与えられた。
真田幸村は豊臣秀吉の仲介で、豊臣秀吉側近の武将大谷吉継の娘を娶る。
真田幸村は従五位下左衛門佐に任ぜられ、豊臣姓を許された。 |
文禄4年
正月3日、豊臣秀吉は自ら上野国草津温泉に湯治するため、甲斐国主浅野幸長ほかに御座所の普請を命じ、
湯治中の周辺城郭の警護番役や道中饗応役を諸大名に割り付けている。
上田城には森忠政、沼田城には京極高知が割り付けられ、真田昌幸には松本より浦野を経て真田にいたる間の御座所の饗応、
真田信幸には真田から鎌原を経て草津に至る間の饗応が申し付けられている。
しかし、実際には豊臣秀吉の草津湯治が実現した形跡は見出せず、こうした命令は空手形に終わっている。 | 真田昌幸は、吾妻郡の一場右京進に伝馬業を許可する。 豊臣秀次が嫌疑をかけられて一族ことごとく誅殺されており、徳川家康以下有力諸侯28名は、お拾い様(豊臣秀頼)への忠誠を誓う起請文を提出させられている。
慶長2年
10月、豊臣秀吉は下野宇都宮城主の宇都宮国綱の所領を突然没収し、宇都宮国綱は宇喜多秀家に預けられる。
これは領内の検地の結果、宇都宮国綱に不正があったためといわれている。 | 11月8日、その跡地の収納役が真田昌幸と浅野長政に命じられている。
慶長3年
豊臣秀吉が没し、徳川家康の権力が日々に強くなる。
真田昌幸・真田幸村父子は徳川家康に随従して伏見に在住していたが、
徳川家康が大阪に移るに伴い大阪に引っ越している。 |
慶長5年
徳川家康が上杉景勝征伐を名として関東に下ると、真田昌幸はそれに従った。 | 7月21日、真田昌幸が下野国犬伏に陣をとっている時、石田三成の密使が来た。 真田昌幸の妻(山之手殿)は石田三成家臣の宇田頼忠の娘であり、 真田昌幸の娘は宇田頼忠の嫡男宇田頼次(山之手殿の弟)に嫁いでいた。 また、真田幸村の義父大谷吉継も石田三成に与していることから、 真田昌幸・真田幸村父子は石田三成を見殺しにできぬ立場にあった。 真田昌幸・真田幸村父子は即日石田方へ属する決心をし、 徳川の陣を離れて上田城へ急行した。 一方、真田信幸の妻は徳川四天王の1人本多忠勝の娘で、 これまた徳川を裏切ることはできぬ立場にあった。 真田信幸は小山の徳川秀忠の本陣へ駆けつけ、父の離反と自分の異心のないことを告げた。 8月24日、徳川秀忠は宇都宮を発して中山道を西上の途につき、 9月1日、徳川家康は江戸城を発して東海道を西上した。 9月2日、徳川秀忠は小諸城に入り、真田昌幸の招降に数日を空費する。 9月6日、徳川秀忠は真田昌幸・真田幸村の籠る上田城を攻めたが、城壁近くへおびき寄せられて 反撃され、手痛い損害を受けた。 徳川秀忠を輔佐して指揮に当たっていた本多正信は諸隊の軍令違反を厳しく責め、 大久保忠隣旗奉行の杉文勝、牧野康成旗奉行の熱(にえ)掃部に死を命じた。 牧野康成は先の上田城攻めにも加わっており、二度にわたって貧乏くじを引いたことになる。 敵将を前にして味方の重要な地位にある者を自殺させるなど、 徳川勢の混乱ぶりが伺われる。 空しく数日を送った徳川秀忠は上田城攻略の見込みが立たぬと見て、 押さえの軍を残して上方へ急行したが、ついに関ヶ原の合戦には間に合わなかった。 徳川秀忠率いる酒井氏・榊原氏・本多氏・大久保氏ら譜代の精兵3万8000、 諸大名軍3万、合せて7万の大軍が潮のように襲いかかったわけだが、 城を陥すことはできず、やむなく徳川家康の本隊の後を追ったが、 関ヶ原に辿りついた時、すでに合戦は終わっていたといわけである。 しかし、関ヶ原合戦は石田方の大敗に終り、 戦後、真田信幸は恩賞にかえて父弟の助命を乞い、 真田昌幸と真田幸村は死一等を減じられて高野山へ流された。 池田長門守以下16名の随臣の名がみえる。 真田信幸は「真田信之」と改名する。
慶長15年
徳川家康は堺の鉄砲鍛冶屋辻家に大砲の購入を注文する。
すでに豊臣家討伐の準備をこまめに始めていたことになる。 |
慶長16年
6月4日、真田昌幸は山麓の九度山村で65歳で死去。 | 真田幸村は木村綱茂や姉婿小山田茂誠(上原茂誠)宛ての手紙には、 気取りや強がりもなく、配所の心細い暮らしを正直に述べている。 真田昌幸の一周忌がすんで後、国許からついてきていた16人の家臣はほとんど 信濃国に帰ったが、高梨内記や青柳清庵らは残った。
慶長18年
6月、徳川家康が大砲購入の契約をする。 |
慶長19年
5月25日、徳川家康は大砲とともに火薬や鉛を購入した。
徳川家康は、京都方広寺大仏殿の釣鐘に刻まれた「国家安康」「君臣豊楽」は
徳川家康を呪い、豊臣家を君主として末長く豊臣の世を楽しむためだという。
大人気ない言いがかりをつけて大阪討伐の口実をでっち上げた。 | 10月9日、豊臣秀頼の使者が大金(現在の金額にして30億)を持って 配所を訪れ、真田幸村の大阪入城を勧めた。 紀伊の国主浅野長晟は、かねて真田幸村の動向に気をつけるよう九度山辺りの名主や 年寄りに命じていたが、 真田幸村は身辺を去らなかった家来と家族を連れてどうどうと山を下り、大阪城へ入城した。 近郷近在の名主や年寄りらを数百人集めて大盤振舞いをし、 連中が酔いつぶれているすきに九度山を脱出したとも伝えられる。 大阪城では大野治長・大野治房・大野治胤の三兄弟が権力を握り、 勇将・猛卒も少なくないが、何分寄集めで団結力が甚だ乏しく、 ことに首脳部の指揮能力は薄弱であった。 大阪城に入った知名度の高い武将といえば、真田幸村のほかに 長宗我部宮内少輔盛親、後藤又兵衛基次などがいたが、大名は1人としていなかった。 大阪城中では淀殿が軍議にも何かと口出しをし、真田幸村ら浪人を疎んじていた。 真田幸村の出撃論は無視され、籠城戦にも 大野治長、後藤又兵衛、木村長門守重成、渡辺内蔵助、明石掃部助、毛利主馬、 長宗我部盛親、毛利豊前守、仙石豊前守らは絶対的な一致団結の精神を欠いていた。 11月19日、戦が始まる。 12月4日、真田丸に籠って徳川方を撃破する。 石川康勝の火薬桶の中に火縄を誤って落としたため大爆発。 城内の内応者の合図と早合点した前田・松平・井伊隊は突撃したが 真田隊の思うがままの標的になって撃破された。 12月6日、小幡勘兵衛の内応を未然に防ぎ、黒門口で徳川家康本陣を大混乱に陥らす。 12月11日、面子にかけて徳川家康は全軍で真田丸を攻撃。 徳川家康が指揮していた井楼は望月六郎の放った大筒で吹き飛んだ。 徳川家康は運よく井楼から下りていて命を助かった。 徳川家康は作戦を中止して茶臼山の本陣へ帰った。 真田信尹が真田幸村を勧誘しにきた。 12月20日、和議が成立。
元和元年
4月29日、塙団右衛門が浅野長晟との合戦で戦死した。 | 5月5日、徳川家康が出陣命令を下す。 5月6日、道明寺合戦で後藤又兵衛・薄田隼人らが戦死。 真田幸村は徳川軍総大将水野勝成・本多忠政・松平忠明・伊達政宗と激闘する。 伊達政宗隊と善戦していたが、豊臣秀頼からの撤退命令が出された。 真田幸村は、もっとも困難な殿を勤めて城中へ退いた。 徳川方は撤退する真田隊に結局手を出せなかったという。 5月7日、真田幸村は嫡男真田大助を大阪城へ帰し、豊臣秀頼に二心のないことを証明した。 真田隊の主だった武将は 真田与左衛門・江原右近・大谷大学・御宿政友・細川興秋・福富平蔵・渡辺内蔵助など 3500の精鋭であった。 対峙する徳川方は前日の藤堂・井伊両隊が苦戦しているのを見ながら合力しなかった ために徳川家康からこっぴどく叱責をうけた松平忠直であった。 最後の合戦に真田隊は目指すは「家康の首」だけを合言葉に1つの火の玉となって 徳川家康の本陣に襲いかかり、旗本を追い散らし、徳川家康を危機に陥れた。 3度にわたって突撃を繰り返した真田幸村は、さすがに手傷を負い、 鉄砲隊頭の西尾久作に討ちとられた。享年49歳。 5月8日、嫡男真田大助は豊臣秀頼に殉死した。享年16歳である。 |